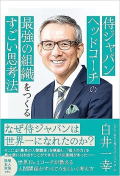コーチングについて
2013年11月10日
ビジネスコーチングは、
たくさんの企業やスポーツチームでも
取り入れられています。
ファイターズでも2001年以降は、
他のチームに先駆けて取り入れ、
選手育成に活用してきました。
当時は指導者の勉強の一貫で、
コーチングの専門的研修を受けたり、
メンタルや動作解析などの学びも、
何度も繰り返していました。
指導者自らが学び、
成長することこそが、
選手の成長につながると、
皆が意識していました。
ティーチング、コーチング、
カウンセリングを効果的に使い分け、
選手の成長に貢献することが、
我々指導者の役割です。
そのためには、
やはり学び続けることが必要不可欠です。
特にコーチングは、
体罰問題でも分かるように、
スポーツ界ほど遅れています。
指示命令恫喝型指導方法は、
いまだに根強く残っています。
これはコーチング自体を知らない、
学んでいないことが原因です。
その一方でコーチングと厳しさや厳格さは、
相反するものと捉えられていますが、
選手の成長やチームの成功には、
両方とも欠かせない要素です。
ティーチングやコーチング、
カウンセリングも同様で、
必要に応じて使い分けることが大切です。
厳しさと楽しさ、
自由と規律、
高いレベルでのバランスを保つことが、
成長、成功につながります。
選手の成長、
チームの成功に本当に必要なのは何なのか、
そこに焦点を合わせることですね。
選手の成長をサポートするには、
指導者自らの成長は必要不可欠ですので、
これからも学び続けます。
たくさんの企業やスポーツチームでも
取り入れられています。
ファイターズでも2001年以降は、
他のチームに先駆けて取り入れ、
選手育成に活用してきました。
当時は指導者の勉強の一貫で、
コーチングの専門的研修を受けたり、
メンタルや動作解析などの学びも、
何度も繰り返していました。
指導者自らが学び、
成長することこそが、
選手の成長につながると、
皆が意識していました。
ティーチング、コーチング、
カウンセリングを効果的に使い分け、
選手の成長に貢献することが、
我々指導者の役割です。
そのためには、
やはり学び続けることが必要不可欠です。
特にコーチングは、
体罰問題でも分かるように、
スポーツ界ほど遅れています。
指示命令恫喝型指導方法は、
いまだに根強く残っています。
これはコーチング自体を知らない、
学んでいないことが原因です。
その一方でコーチングと厳しさや厳格さは、
相反するものと捉えられていますが、
選手の成長やチームの成功には、
両方とも欠かせない要素です。
ティーチングやコーチング、
カウンセリングも同様で、
必要に応じて使い分けることが大切です。
厳しさと楽しさ、
自由と規律、
高いレベルでのバランスを保つことが、
成長、成功につながります。
選手の成長、
チームの成功に本当に必要なのは何なのか、
そこに焦点を合わせることですね。
選手の成長をサポートするには、
指導者自らの成長は必要不可欠ですので、
これからも学び続けます。
コーチングについて
2010年06月18日
今日は岐阜県で講演です。
新幹線で岐阜羽島まで行き、
そこからさらに1時間以上車で移動します。
夜7時からの講演で、対象者はほとんどが指導者です。
アマチュアの指導者の皆さんは、
仕事を終了した後にも選手指導や勉強会に参加して、
子供達のために一生懸命活動しています。
指導者らしさといえば、
指示命令恫喝型をイメージする方が多くいますが、
これでは選手のためにはなりません。
指導者は指導者らしくすることが大切なのではなく、
選手のためになれるのかどうかが大切なのです。
怒ったり、教えたり、猛練習を課したりすることは、
ある意味指導者としては、
厳しい、理論家、情熱的と評価されます。
また指導者としては心地いいことも確かです。
結果に対して叱責すれば、選手は萎縮してミスを重ねます。
また問題点に対して教えれば教えるほど選手が受身になり、
自分で考えたり創意工夫する事がなくなります。
そして猛練習を課せば課すほど、やらされる意識が強くなり、
猛練習に耐えたり、消化することが目的となります。
結果を受け入れ、常に選手を励まし、
前向きな声がけをすることは、
選手が積極的にプレーすることにつながります。
問題点に対して教えるのではなく、
選手が自らが考え、気づきを与えるには、
見守ることや、一緒に考えたり質問をしてみることも大切です。
そして選手は上達するために練習が必要なことは、
選手自身が一番よく知っています。
猛練習を課すことではなく、
自らが猛練習に取り組むようになることが、
上達という練習の本来の目的達成につながります。
向上心に溢れる選手は、
自らが考え、行動を起こすものです。
指導者は選手の向上心、
やる気を引き出し、育てることに意識を持つべきだと思います。
励まし、見守り、サポートすることは、
指導者の動きとしては物足りないと考える方もいるかもしれません。
しかし選手の立場に立てば、
このような指導者のほうがありがいのではないでしょうか?
指導者が従来のような指示命令型の指導者らしさを目指すのではなく、
指導者は指導者としてあるべき姿、
選手にとってどうあるべきかが大切です。
その中には毅然とした厳しさも必要ですし、
溢れ出る愛情も必要です。
結果ではなく、「全力を尽くしたかどうか」、
「意識すれば出来ることに対して惜しみなく労力を払えるかどうか」
に対して毅然とした厳しさを持ち続けることのできる指導者。
選手の成長をサポートできる、
そして選手の成功を何より喜べる指導者。
これが目指すべき私の指導者像です。
今日の講演でもこのような話をしたいと思っています。
そして話せば話すほど、自分自身の気づきでもあるのです。
新幹線で岐阜羽島まで行き、
そこからさらに1時間以上車で移動します。
夜7時からの講演で、対象者はほとんどが指導者です。
アマチュアの指導者の皆さんは、
仕事を終了した後にも選手指導や勉強会に参加して、
子供達のために一生懸命活動しています。
指導者らしさといえば、
指示命令恫喝型をイメージする方が多くいますが、
これでは選手のためにはなりません。
指導者は指導者らしくすることが大切なのではなく、
選手のためになれるのかどうかが大切なのです。
怒ったり、教えたり、猛練習を課したりすることは、
ある意味指導者としては、
厳しい、理論家、情熱的と評価されます。
また指導者としては心地いいことも確かです。
結果に対して叱責すれば、選手は萎縮してミスを重ねます。
また問題点に対して教えれば教えるほど選手が受身になり、
自分で考えたり創意工夫する事がなくなります。
そして猛練習を課せば課すほど、やらされる意識が強くなり、
猛練習に耐えたり、消化することが目的となります。
結果を受け入れ、常に選手を励まし、
前向きな声がけをすることは、
選手が積極的にプレーすることにつながります。
問題点に対して教えるのではなく、
選手が自らが考え、気づきを与えるには、
見守ることや、一緒に考えたり質問をしてみることも大切です。
そして選手は上達するために練習が必要なことは、
選手自身が一番よく知っています。
猛練習を課すことではなく、
自らが猛練習に取り組むようになることが、
上達という練習の本来の目的達成につながります。
向上心に溢れる選手は、
自らが考え、行動を起こすものです。
指導者は選手の向上心、
やる気を引き出し、育てることに意識を持つべきだと思います。
励まし、見守り、サポートすることは、
指導者の動きとしては物足りないと考える方もいるかもしれません。
しかし選手の立場に立てば、
このような指導者のほうがありがいのではないでしょうか?
指導者が従来のような指示命令型の指導者らしさを目指すのではなく、
指導者は指導者としてあるべき姿、
選手にとってどうあるべきかが大切です。
その中には毅然とした厳しさも必要ですし、
溢れ出る愛情も必要です。
結果ではなく、「全力を尽くしたかどうか」、
「意識すれば出来ることに対して惜しみなく労力を払えるかどうか」
に対して毅然とした厳しさを持ち続けることのできる指導者。
選手の成長をサポートできる、
そして選手の成功を何より喜べる指導者。
これが目指すべき私の指導者像です。
今日の講演でもこのような話をしたいと思っています。
そして話せば話すほど、自分自身の気づきでもあるのです。
コーチングについて
2009年06月29日
今日は梅雨の中休みか、
快晴でとてもさわやかな朝です。
雨は雨なりのよさがありますが、
快晴は心までウキウキして前向きになれますね。
長男の野球チームはまだ決まっていません。
先日体験入団をしてきたのですが、
なかなか思うようなチームに出会っていません。
自分でチームを作らなければいけないかな?
なんて思ってしまうくらい、
深刻な状況があるのが現状です。
野球の練習に行くのが楽しくてたまらない、
まさしく今日の天気のようなウキウキしてしまうチーム作り、
これが最も求めているものです。
だらだらと6時間以上も、
怒る、教える(間違えた技術を)、やらせる練習では、
子供の可能性を引き出すことにはなりません。
先週日曜日、長野で少年野球教室を兼ねて、
指導者研修を行ないました。
実際に一つのチームの選手を私が指導し、
その指導方法について指導者に説明を加えながら、
練習を進めました。
キャッチボールが満足にできない子供たちに、
延々とキャッチボールをやらすよりは、
できることから始めました。
運動会で玉入れ競争がありますが、
そのときに投げ方を教える先生はいません。
教えてもらわなくても、かごにボールを投げ込むことはできます。
しかし、キャッチボールになると上手く投げれないのです。
これはまだ捕ることのできない相手に対してボールを投げるのですから、
怪我をさせてはいけないのでコントロール、
スピードなど多くの要素が必要になります。
しかし玉入れ競争には、
相手がかごなので当然怪我はありません。
そして入らなくても自分で拾い、また投げればいいのですから、
ただかごにボールを投げ込むことに集中できます。
そこに競争があれば、
より真剣に、そして楽しむことができます。
投げ方を教えることより、
まだ成立しないキャッチボールを繰り返すより、
玉入れ競争のかごを高い位置ではなく、
キャッチボールの的なるような位置に設置して、
そこに10球投げて何球入るのかなどの競争をすればいいのです。
子供たちは真剣、そして楽しみながら、
かご入るように工夫して投げるようになります。
そしてそこには多くの成功体験が生まれ、
その成功体験は、もっと難しいことへの挑戦意欲につながります。
挑戦意欲が湧けば、
距離を伸ばしたり、的を小さくしたりと、
難易度を高めていけばいいのです。
長野の野球教室では、
かごの代わりにティバッティグ用のネット(真ん中に穴が開いている)に向かって、
投げることから始めました。
キャッチボールをしていた時よりも、
とても理に適ったスムーズなフォームで、
スピードのあるボールを、何球も、楽しそうに投げ続けました。
ほんの少し投げることに集中できる状況を作り出すだけで、
十分に投げる練習になるのです。
キャッチボールだけが投げる練習ではないということです。
これはほんの一例ですが、
子供の意欲を高め、意識を集中させれば、
子供の可能性を引き出すことにつながります。
真剣に、楽しく、工夫するような状況を作り出すことも、
コーチングといえるのです。
今朝は天気にコーチングをしていただき、
ウキウキ、ワクワクとした気持ちでスタートを切ることができました。
快晴でとてもさわやかな朝です。
雨は雨なりのよさがありますが、
快晴は心までウキウキして前向きになれますね。
長男の野球チームはまだ決まっていません。
先日体験入団をしてきたのですが、
なかなか思うようなチームに出会っていません。
自分でチームを作らなければいけないかな?
なんて思ってしまうくらい、
深刻な状況があるのが現状です。
野球の練習に行くのが楽しくてたまらない、
まさしく今日の天気のようなウキウキしてしまうチーム作り、
これが最も求めているものです。
だらだらと6時間以上も、
怒る、教える(間違えた技術を)、やらせる練習では、
子供の可能性を引き出すことにはなりません。
先週日曜日、長野で少年野球教室を兼ねて、
指導者研修を行ないました。
実際に一つのチームの選手を私が指導し、
その指導方法について指導者に説明を加えながら、
練習を進めました。
キャッチボールが満足にできない子供たちに、
延々とキャッチボールをやらすよりは、
できることから始めました。
運動会で玉入れ競争がありますが、
そのときに投げ方を教える先生はいません。
教えてもらわなくても、かごにボールを投げ込むことはできます。
しかし、キャッチボールになると上手く投げれないのです。
これはまだ捕ることのできない相手に対してボールを投げるのですから、
怪我をさせてはいけないのでコントロール、
スピードなど多くの要素が必要になります。
しかし玉入れ競争には、
相手がかごなので当然怪我はありません。
そして入らなくても自分で拾い、また投げればいいのですから、
ただかごにボールを投げ込むことに集中できます。
そこに競争があれば、
より真剣に、そして楽しむことができます。
投げ方を教えることより、
まだ成立しないキャッチボールを繰り返すより、
玉入れ競争のかごを高い位置ではなく、
キャッチボールの的なるような位置に設置して、
そこに10球投げて何球入るのかなどの競争をすればいいのです。
子供たちは真剣、そして楽しみながら、
かご入るように工夫して投げるようになります。
そしてそこには多くの成功体験が生まれ、
その成功体験は、もっと難しいことへの挑戦意欲につながります。
挑戦意欲が湧けば、
距離を伸ばしたり、的を小さくしたりと、
難易度を高めていけばいいのです。
長野の野球教室では、
かごの代わりにティバッティグ用のネット(真ん中に穴が開いている)に向かって、
投げることから始めました。
キャッチボールをしていた時よりも、
とても理に適ったスムーズなフォームで、
スピードのあるボールを、何球も、楽しそうに投げ続けました。
ほんの少し投げることに集中できる状況を作り出すだけで、
十分に投げる練習になるのです。
キャッチボールだけが投げる練習ではないということです。
これはほんの一例ですが、
子供の意欲を高め、意識を集中させれば、
子供の可能性を引き出すことにつながります。
真剣に、楽しく、工夫するような状況を作り出すことも、
コーチングといえるのです。
今朝は天気にコーチングをしていただき、
ウキウキ、ワクワクとした気持ちでスタートを切ることができました。
コーチングについて
2009年05月15日
コーチングについては多くのコメントをいただき、
多くの問題や疑問に直面していることを改めて感じました。
近年は書店で「コーチング」関連の書籍が多く見られるようになりした。
私も2002年に「コーチング」の本を購入して読んでいます。
当時はビジネスコーチングの本でしたが、
この本を読んだときに、
2001年から取り組んでいるファイターズファームの指導方法そのものだと感じました。
選手の成長をサポートすることとは「選手のやる気」を引き出し、
大きく膨らましてあげることにより、
前向きな、積極的な、自発的な取り組みこそが成長を促す、
チームが強くなるための指導方法だと考えて実践していました。
これまでの指導者らしさから見れば、
ずいぶんとかけ離れた指導方法であり、
多くの批判や反発があったことも事実です。
しかし、指示命令、恫喝方の指導をしていたときよりも、
選手が前向きに、積極的にプレーし、
自発的な取り組みによる練習の質や量は格段に高くなりました。
36勝64敗のぶっちぎりの最下位と結果がでなかった2001年でも、
選手の意識、チームの方向性には手応えを感じていました。
(その分批判や反発が大きかったのですが)
伸びる選手はどのような選手なのか?
伸びる選手は「やる気」に満ち溢れて、
前向きに、積極的に、自発的に取り組んでいる選手ではないのだろうか。
それならば選手の「やる気」を引き出し、膨らませてあげることが、
指導者としての頑張る方向性ではないのだろうか。
指示命令、恫喝は「やる気」をそいではいないだろうか?
そして萎縮や義務的な練習につながっていないだろうか?
と考えたことがスタートでした。
しかし、結果と成果が同時に出ない現実に直面していたときに、
2002年に「コーチング」という考え方に知ったことは、
試行錯誤しながら指導していたファーム指導者にとっては大きな力となりました。
「間違いないんだ」「この考え方で大丈夫なんだ」
と強い確信に変わったときでした。
当時の野球界では異質な存在でしたが、
これこそがこれからの指導方法であると確信を持ち、
あらゆる批判や逆風に立ち向かっていきました。
新しいことに挑戦するときは、いろんな困難が立ちはだかりますが、
新しいことに挑戦することは楽しみであり遣り甲斐でした。
指導者らしさ(怒る、教える、やらせる)が大切なのではなく、
選手にとってプラスになる、成長を促せる指導者なることを目指しました。
コーチングの手法は、
選手も指導者も共に楽しく、前向きに、積極的に、
そしてやる気に満ち溢れる、双方向からのコミュニケーションだと思います。
多くの問題や疑問に直面していることを改めて感じました。
近年は書店で「コーチング」関連の書籍が多く見られるようになりした。
私も2002年に「コーチング」の本を購入して読んでいます。
当時はビジネスコーチングの本でしたが、
この本を読んだときに、
2001年から取り組んでいるファイターズファームの指導方法そのものだと感じました。
選手の成長をサポートすることとは「選手のやる気」を引き出し、
大きく膨らましてあげることにより、
前向きな、積極的な、自発的な取り組みこそが成長を促す、
チームが強くなるための指導方法だと考えて実践していました。
これまでの指導者らしさから見れば、
ずいぶんとかけ離れた指導方法であり、
多くの批判や反発があったことも事実です。
しかし、指示命令、恫喝方の指導をしていたときよりも、
選手が前向きに、積極的にプレーし、
自発的な取り組みによる練習の質や量は格段に高くなりました。
36勝64敗のぶっちぎりの最下位と結果がでなかった2001年でも、
選手の意識、チームの方向性には手応えを感じていました。
(その分批判や反発が大きかったのですが)
伸びる選手はどのような選手なのか?
伸びる選手は「やる気」に満ち溢れて、
前向きに、積極的に、自発的に取り組んでいる選手ではないのだろうか。
それならば選手の「やる気」を引き出し、膨らませてあげることが、
指導者としての頑張る方向性ではないのだろうか。
指示命令、恫喝は「やる気」をそいではいないだろうか?
そして萎縮や義務的な練習につながっていないだろうか?
と考えたことがスタートでした。
しかし、結果と成果が同時に出ない現実に直面していたときに、
2002年に「コーチング」という考え方に知ったことは、
試行錯誤しながら指導していたファーム指導者にとっては大きな力となりました。
「間違いないんだ」「この考え方で大丈夫なんだ」
と強い確信に変わったときでした。
当時の野球界では異質な存在でしたが、
これこそがこれからの指導方法であると確信を持ち、
あらゆる批判や逆風に立ち向かっていきました。
新しいことに挑戦するときは、いろんな困難が立ちはだかりますが、
新しいことに挑戦することは楽しみであり遣り甲斐でした。
指導者らしさ(怒る、教える、やらせる)が大切なのではなく、
選手にとってプラスになる、成長を促せる指導者なることを目指しました。
コーチングの手法は、
選手も指導者も共に楽しく、前向きに、積極的に、
そしてやる気に満ち溢れる、双方向からのコミュニケーションだと思います。
コーチングについて
2009年05月13日
昨日から多くの人にコーチングをしていただきました。
励ましの力、サポートする力、
これこそがコーチングだと改めて感じました。
目指すところへの導き、
目指すことへのサポート、
そしてたくさんの励ましは、
何よりのエネルギーとなりました。
私が目指すべき方向に向かって、
これからも自分なりの考えや意見を発信する力が湧いてきました。
本当にありがとうございました。
少年野球、子供への指導方法への質問、
疑問は本当に切実な問題だと思います。
正しい技術論、トレーニング論、コーチングを含めた指導方法など、
解決しなければいけないことがたくさんあるのが現実です。
皆さんが疑問に思っているように、
朝から晩までの練習は必要なのでしょうか。
身体を壊すほどの猛練習は必要なのでしょうか。
大人と子供の関係で、恫喝するような指導方法は正しいのでしょうか。
時間と労力を使い、
無償で子供を指導する姿勢は本当に素晴らしいことだと思います。
一生懸命に指導することも素晴らしいことだと思います。
その方向性がどのような方向に向かっているかは大切ですが。
子供の限りない可能性を引き出し、
将来へつなげることが、指導者としての務めだと思います。
そのために指導することは、
朝から晩までの、身体が壊れるほどの猛練習、
大声を張りはげて恫喝するような指導方法より、
もっと時間と労力のかかることかもしれません。
本当に根気のいる、時間のかかる指導方法かもしれませんが、
何より子供の可能性を引き出し、将来につなげることができたなら、
いくら時間をかけようが、どれだけの労力を払おうが、
これに勝る大きな喜びはありません。
上手くなること、試合で勝つこと、
猛練習に打ち克つ精神力も必要でしょうが、
そのための猛練習や恫喝型指導方法より、
子供が「もっと上手くなりたい」「たくさん試合に勝ちたい(子供たちが自発的に)」「もっと練習したい」
と思えるような指導方法があるとすれば、
どちらが有効でしょうか。
「練習が楽しい」「試合が楽しい」、
そのためには「苦しくても頑張る」「あきらめずに頑張る」、
ことを子供自身がそのように思えたときの精神的な成長は、
少なくとも恫喝されながらの頑張りよりははるかに大きいと思います。
私自身も、長男の可能性を引き出してくれるような、
将来への道を開くような指導をしている野球チームを探しています。
またそのような指導を目指す人達と共に勉強しながら、
同じ方向を目指す指導者が一人でも多くなることを望んでいます。
そのためにも一日も早く指導者や、
今でも野球のプレーを楽しんでいる人達、
そして子供をもつ父親の皆さん達と一緒に、
勉強会や実際に練習をできるような講習会を開催したいと動いています。
もう少し時間をいただければと思います。
励ましの力、サポートする力、
これこそがコーチングだと改めて感じました。
目指すところへの導き、
目指すことへのサポート、
そしてたくさんの励ましは、
何よりのエネルギーとなりました。
私が目指すべき方向に向かって、
これからも自分なりの考えや意見を発信する力が湧いてきました。
本当にありがとうございました。
少年野球、子供への指導方法への質問、
疑問は本当に切実な問題だと思います。
正しい技術論、トレーニング論、コーチングを含めた指導方法など、
解決しなければいけないことがたくさんあるのが現実です。
皆さんが疑問に思っているように、
朝から晩までの練習は必要なのでしょうか。
身体を壊すほどの猛練習は必要なのでしょうか。
大人と子供の関係で、恫喝するような指導方法は正しいのでしょうか。
時間と労力を使い、
無償で子供を指導する姿勢は本当に素晴らしいことだと思います。
一生懸命に指導することも素晴らしいことだと思います。
その方向性がどのような方向に向かっているかは大切ですが。
子供の限りない可能性を引き出し、
将来へつなげることが、指導者としての務めだと思います。
そのために指導することは、
朝から晩までの、身体が壊れるほどの猛練習、
大声を張りはげて恫喝するような指導方法より、
もっと時間と労力のかかることかもしれません。
本当に根気のいる、時間のかかる指導方法かもしれませんが、
何より子供の可能性を引き出し、将来につなげることができたなら、
いくら時間をかけようが、どれだけの労力を払おうが、
これに勝る大きな喜びはありません。
上手くなること、試合で勝つこと、
猛練習に打ち克つ精神力も必要でしょうが、
そのための猛練習や恫喝型指導方法より、
子供が「もっと上手くなりたい」「たくさん試合に勝ちたい(子供たちが自発的に)」「もっと練習したい」
と思えるような指導方法があるとすれば、
どちらが有効でしょうか。
「練習が楽しい」「試合が楽しい」、
そのためには「苦しくても頑張る」「あきらめずに頑張る」、
ことを子供自身がそのように思えたときの精神的な成長は、
少なくとも恫喝されながらの頑張りよりははるかに大きいと思います。
私自身も、長男の可能性を引き出してくれるような、
将来への道を開くような指導をしている野球チームを探しています。
またそのような指導を目指す人達と共に勉強しながら、
同じ方向を目指す指導者が一人でも多くなることを望んでいます。
そのためにも一日も早く指導者や、
今でも野球のプレーを楽しんでいる人達、
そして子供をもつ父親の皆さん達と一緒に、
勉強会や実際に練習をできるような講習会を開催したいと動いています。
もう少し時間をいただければと思います。
コーチングについて
2009年04月14日
子供の指導者、
親向けへの指導本の出版を進めてることは
すでに告知しています。
この本の出版と平行して企画しているのが、
実際に子供を指導している方や、
社会人になっても野球が好きで、
今でもプレーを続けている方達を対象の、
野球教室や勉強会の開催です。
野球経験やレベル、また軟式、硬式などは問わずに、
子供の指導へ、
そして野球そのものに情熱を持っている人であれば
誰でも参加できるようにしたいと思っています。
勉強会とともに、実際に実技をしながら技術や指導方法について
ディスカッションする事が最大の目的です。
技術論、トレーニング方法、戦術や戦略、指導方法(コーチング、ティーチング)、
メンタルなど多岐にわたっての勉強会です。
現在は勉強と実技のできる場所や、
指導者や社会人の方が参加できる期日などの調整中です。
子供の指導者であれば、土耀、日耀日の日中は試合があるので、
夕方から夜にかけての時間で、
なお且つ照明施設のある球場か、
室内練習場を探しています。
場所や日時が決まりしだい、
このブログでも詳細をお知らせします。
その時には、一人でも多くの人達に集まっていただきたいと思います。
また3月22日にお約束した次回の講演会についても、
交流戦終了後あたりで調整中です。
こちらのほうも楽しみに待っていてください。
今日のオリックス戦で、パリーグ全球団との対戦になります。
一回りすれば各球団の戦力なども判ります。
オリックスは投手力、特に若手の伸び盛りの投手が多いことが特徴です。
またベテランの野手、特に実績のある外国人選手で強力な打線を構築してます。
優勝争いの有力な候補であることは間違いありません。
このシリーズは、シーズンを占う意味でも重要です。
そして本拠地初勝利もかかっています。
私も球場で観戦したいと思っています。
親向けへの指導本の出版を進めてることは
すでに告知しています。
この本の出版と平行して企画しているのが、
実際に子供を指導している方や、
社会人になっても野球が好きで、
今でもプレーを続けている方達を対象の、
野球教室や勉強会の開催です。
野球経験やレベル、また軟式、硬式などは問わずに、
子供の指導へ、
そして野球そのものに情熱を持っている人であれば
誰でも参加できるようにしたいと思っています。
勉強会とともに、実際に実技をしながら技術や指導方法について
ディスカッションする事が最大の目的です。
技術論、トレーニング方法、戦術や戦略、指導方法(コーチング、ティーチング)、
メンタルなど多岐にわたっての勉強会です。
現在は勉強と実技のできる場所や、
指導者や社会人の方が参加できる期日などの調整中です。
子供の指導者であれば、土耀、日耀日の日中は試合があるので、
夕方から夜にかけての時間で、
なお且つ照明施設のある球場か、
室内練習場を探しています。
場所や日時が決まりしだい、
このブログでも詳細をお知らせします。
その時には、一人でも多くの人達に集まっていただきたいと思います。
また3月22日にお約束した次回の講演会についても、
交流戦終了後あたりで調整中です。
こちらのほうも楽しみに待っていてください。
今日のオリックス戦で、パリーグ全球団との対戦になります。
一回りすれば各球団の戦力なども判ります。
オリックスは投手力、特に若手の伸び盛りの投手が多いことが特徴です。
またベテランの野手、特に実績のある外国人選手で強力な打線を構築してます。
優勝争いの有力な候補であることは間違いありません。
このシリーズは、シーズンを占う意味でも重要です。
そして本拠地初勝利もかかっています。
私も球場で観戦したいと思っています。
コーチングについて
2009年04月09日
今週末は楽しみなイベントが待っています。
それはマスターズ。
石川遼選手が出場していますが、
ゴルファーならば誰でも一度はプレーしてみたいと思う、
オーガスタナショナルが舞台です。
今年はタイガーウッズが復帰後メジャー初戦となるなど、
いつも以上に注目が高く、
私の知人も現地に観戦に出かけました。
ゴルフはメンタルなスポーツであり、
技術や体力だけでなく、心の強さがそのまま成績に現れます。
石川遼選手は、17歳にもかかわらず素晴らしい言葉を使います。
前向きで、そして整理されたコメントが多く、
メンタル面での強さも感じさせます。
石川遼選手は、子供の頃から父親が指導しながらここまで成長してきました。
技術だけでなく、マナーや心構えなども厳しく指導してきたようです。
タイガーウッズも、子供の頃は父親が指導していたようです。
現在の彼らがあるのは、
父親である指導者の方向性が正しかったことの証明でしょう。
それくらい子供の頃は、
父親や指導者の影響は大きいように思います。
最近バッティングセンターに通っていますが、
WBCの影響かとても混雑するようになっています。
また親子連れが多いことも目に付きます。
私もその親子連れの仲間ですが。(笑)
元プロ野球選手でありコーチである私に気が付く人はほとんどいません。
それが、私も気軽に足を運べる理由ですが、
少し気になることがあります。
混んでいることもあり、
順番に交代しながらバッティングをするのですが、
子供に教えすぎている父親が多いのです。
子供に一生懸命教えているのですが、
教えれば教えるほど打てなくなるのです。
その教えが正しければいいのですが、
ほとんどが間違えた技術指導をしながら、
どんどん子供が打てなくなっているのです。
最後は半泣きになるくらい、
強制的に、怒鳴り散らして指導しています。
一球一球、「もっと上からバットを出せ」、「フライを打つな」、
「腰を回せ」、「身体を開くな」、「ボールを見ろ」、「頭を動かすな」
「ポイントを前にしろ」、「泳ぐな」、
などとしつこいくらいに教えているのです。
強制指示、否定命令的な言葉の連続です。
「このようにしろ」は強制指示であり、
「何々してはいけない」否定命令です。
楽しみも喜びもでてこない、
上達の妨げになるのが、
この強制指示であり否定命令です。
バットを上から出せば出すほど、フライになる可能性が高く、
腰を回せば回すほど、身体の開き早くなります。
一度に両方の指導を受けている子供は、
何をしていいかわからなくなってきます。
プロ野球の世界でも、同じような指導をしている人が多いのですが、
これでは子供の可能性を引き出す指導とはいえません。
それもほとんどが、何の疑いもなく熱心に指導しているのです。
この指導法方法を少し変えてみるだけで、
子供の可能性はもっと大きく伸びる気がします。
今日は、この子供の指導者向け、父親向けの出版の打ち合わせです。
昨年から文章や内容はできているのですが、
できるだけ簡単に、解りやすい本にしたいので、
出版が遅れています。
子供が楽しく、喜びを感じることのできる指導方法、
正しい技術指導ができるようなお手伝いができればと思っています。
子供の無限大の可能性を引き出すことは、
指導者や親の大切な役割です。
私もその一人としてバッティグセンターに通い、
子供を指導しながら確認したり勉強しています。
バッティングセンターの混雑に代表されるように、
WBCで盛り上がっている野球熱が、
もっと高く、そして長く続いて欲しいと思っています。
それはマスターズ。
石川遼選手が出場していますが、
ゴルファーならば誰でも一度はプレーしてみたいと思う、
オーガスタナショナルが舞台です。
今年はタイガーウッズが復帰後メジャー初戦となるなど、
いつも以上に注目が高く、
私の知人も現地に観戦に出かけました。
ゴルフはメンタルなスポーツであり、
技術や体力だけでなく、心の強さがそのまま成績に現れます。
石川遼選手は、17歳にもかかわらず素晴らしい言葉を使います。
前向きで、そして整理されたコメントが多く、
メンタル面での強さも感じさせます。
石川遼選手は、子供の頃から父親が指導しながらここまで成長してきました。
技術だけでなく、マナーや心構えなども厳しく指導してきたようです。
タイガーウッズも、子供の頃は父親が指導していたようです。
現在の彼らがあるのは、
父親である指導者の方向性が正しかったことの証明でしょう。
それくらい子供の頃は、
父親や指導者の影響は大きいように思います。
最近バッティングセンターに通っていますが、
WBCの影響かとても混雑するようになっています。
また親子連れが多いことも目に付きます。
私もその親子連れの仲間ですが。(笑)
元プロ野球選手でありコーチである私に気が付く人はほとんどいません。
それが、私も気軽に足を運べる理由ですが、
少し気になることがあります。
混んでいることもあり、
順番に交代しながらバッティングをするのですが、
子供に教えすぎている父親が多いのです。
子供に一生懸命教えているのですが、
教えれば教えるほど打てなくなるのです。
その教えが正しければいいのですが、
ほとんどが間違えた技術指導をしながら、
どんどん子供が打てなくなっているのです。
最後は半泣きになるくらい、
強制的に、怒鳴り散らして指導しています。
一球一球、「もっと上からバットを出せ」、「フライを打つな」、
「腰を回せ」、「身体を開くな」、「ボールを見ろ」、「頭を動かすな」
「ポイントを前にしろ」、「泳ぐな」、
などとしつこいくらいに教えているのです。
強制指示、否定命令的な言葉の連続です。
「このようにしろ」は強制指示であり、
「何々してはいけない」否定命令です。
楽しみも喜びもでてこない、
上達の妨げになるのが、
この強制指示であり否定命令です。
バットを上から出せば出すほど、フライになる可能性が高く、
腰を回せば回すほど、身体の開き早くなります。
一度に両方の指導を受けている子供は、
何をしていいかわからなくなってきます。
プロ野球の世界でも、同じような指導をしている人が多いのですが、
これでは子供の可能性を引き出す指導とはいえません。
それもほとんどが、何の疑いもなく熱心に指導しているのです。
この指導法方法を少し変えてみるだけで、
子供の可能性はもっと大きく伸びる気がします。
今日は、この子供の指導者向け、父親向けの出版の打ち合わせです。
昨年から文章や内容はできているのですが、
できるだけ簡単に、解りやすい本にしたいので、
出版が遅れています。
子供が楽しく、喜びを感じることのできる指導方法、
正しい技術指導ができるようなお手伝いができればと思っています。
子供の無限大の可能性を引き出すことは、
指導者や親の大切な役割です。
私もその一人としてバッティグセンターに通い、
子供を指導しながら確認したり勉強しています。
バッティングセンターの混雑に代表されるように、
WBCで盛り上がっている野球熱が、
もっと高く、そして長く続いて欲しいと思っています。
コーチング
2008年12月01日
断食に入っています。
予定を繰り上げて土曜日の夜からはじめて、
今日の午後に断食施設に入りました。
昨夜の我が家の夕食はカレー、
そして今日新幹線で移動中に、
隣の席の人はすき焼き弁当を食べていました。
とても食欲をそそる匂いに耐えての断食は、
精神修行にもなります(笑)。
自分を律することは難しいものです。
しかし、自ら進んで取り組んだこと、
必ず達成したい目標を自分で掲げたとき、
自分を律することは難しくありません。
今回の断食も、
今年不規則なスケジュール、
そしてホテル生活も多く食生活も万全ではありませんでした。
体調管理、そして体重コントロール、
心身リセットのためにも断食が必要と自分自身で判断したからです。
誰かに断食を命令されたのであれば、
途中で挫折したり、
目を盗んで食べることもあるかもしれません。
当然我慢は強いられるわけですから、
結構難しいものです。
しかし、自ら進んで取り組んでいますから、
どんなに大変でも乗り越えられるのです。
目標も同じで、自分自身で掲げ、
絶対に達成したい目標であれば、
どんな困難も乗り越えることができ、
そして達成できるのです。
誰かに指示されるのか、
それとも自ら取り組むかでは大きな違いがあります。
これをいろんな場面に当てはめると、
自ら進んで行動を起こし、
自ら進んで目標を立て、達成に向けて取り組んでいれば、
誰からも指示されないのです。
自分を取り巻く環境に左右されるのではなく、
環境を作っていけばいいのです。
コーチングも同じで、
選手自ら進んで取り組める環境を作り出せればいいのです。
指示、命令、恫喝、注意ではこの環境は作れません。
コーチの重要な役割は、
環境づくりといえるのではないでしょうか。
断食に耐えながら、自分を律することの大切さ、
そして自分を律するためには、
自ら取り組むことの重要性を再認識しています。
予定を繰り上げて土曜日の夜からはじめて、
今日の午後に断食施設に入りました。
昨夜の我が家の夕食はカレー、
そして今日新幹線で移動中に、
隣の席の人はすき焼き弁当を食べていました。
とても食欲をそそる匂いに耐えての断食は、
精神修行にもなります(笑)。
自分を律することは難しいものです。
しかし、自ら進んで取り組んだこと、
必ず達成したい目標を自分で掲げたとき、
自分を律することは難しくありません。
今回の断食も、
今年不規則なスケジュール、
そしてホテル生活も多く食生活も万全ではありませんでした。
体調管理、そして体重コントロール、
心身リセットのためにも断食が必要と自分自身で判断したからです。
誰かに断食を命令されたのであれば、
途中で挫折したり、
目を盗んで食べることもあるかもしれません。
当然我慢は強いられるわけですから、
結構難しいものです。
しかし、自ら進んで取り組んでいますから、
どんなに大変でも乗り越えられるのです。
目標も同じで、自分自身で掲げ、
絶対に達成したい目標であれば、
どんな困難も乗り越えることができ、
そして達成できるのです。
誰かに指示されるのか、
それとも自ら取り組むかでは大きな違いがあります。
これをいろんな場面に当てはめると、
自ら進んで行動を起こし、
自ら進んで目標を立て、達成に向けて取り組んでいれば、
誰からも指示されないのです。
自分を取り巻く環境に左右されるのではなく、
環境を作っていけばいいのです。
コーチングも同じで、
選手自ら進んで取り組める環境を作り出せればいいのです。
指示、命令、恫喝、注意ではこの環境は作れません。
コーチの重要な役割は、
環境づくりといえるのではないでしょうか。
断食に耐えながら、自分を律することの大切さ、
そして自分を律するためには、
自ら取り組むことの重要性を再認識しています。
コーチングについて
2008年11月07日
私のブログタイトルはナイストライ!
大好きな言葉の一つです。
行動を起こせば成功か失敗の結果がでてきます。
成功には歓喜と賞賛、
失敗には落胆と誹謗中傷がついて回ります。
しかし、成功は未来永劫の成功につながるとは限りません。
また、失敗からは学ぶことも多く、
その学びから次への大きな成功につながることも経験しています。
今起きている結果に対して一喜一憂する必要はないと思います。
行動を起こすから、何らかの結果につながります。
その結果として現れる成功からは、、
油断することなく新たな成功への意欲につなげ、
失敗からは、多くのことを学び、
次への成功へつなげることに意識を向けていけば、
すべての結果はプラス材料になるのです。
落胆する必要も、誹謗中傷を気にする必要もないと思います。
行動を起こすからこそ、
得るものが多いのです。
失敗を恐れて行動を起こすことをやめれば、
どこにも成長は生まれません。
だからこそ行動を起こすのです。
結果ではなく、行動を起こすことに意味があるからこそ
「ナイストライ」なのです。
アメリカ留学中にコーチの人達が、
成功には「グッドジャブ」
失敗には「ナイストライ」
と声をかけていました。
どちらもポジティブな言葉であり、考え方です。
結果に対して、
「怒る、教える、やらせる」の、
スリーパンチは行動を起こすことを躊躇させてしまいます。
日本のスポーツ界に必要な言葉、考え方は
「ナイストライ」であることを教えてくれました。
結果を恐れず行動を起こすこと。
そしてそのすべての結果を受け入れ、
次への成功へつなげること。
「ナイストライ」
とても心地よい響きのある、
そして前向きな気持ちにさせてくれる、
素晴らしい言葉だと思いませんか。
だから私のブログタイトルは、
ナイストライ!
なのです。
大好きな言葉の一つです。
行動を起こせば成功か失敗の結果がでてきます。
成功には歓喜と賞賛、
失敗には落胆と誹謗中傷がついて回ります。
しかし、成功は未来永劫の成功につながるとは限りません。
また、失敗からは学ぶことも多く、
その学びから次への大きな成功につながることも経験しています。
今起きている結果に対して一喜一憂する必要はないと思います。
行動を起こすから、何らかの結果につながります。
その結果として現れる成功からは、、
油断することなく新たな成功への意欲につなげ、
失敗からは、多くのことを学び、
次への成功へつなげることに意識を向けていけば、
すべての結果はプラス材料になるのです。
落胆する必要も、誹謗中傷を気にする必要もないと思います。
行動を起こすからこそ、
得るものが多いのです。
失敗を恐れて行動を起こすことをやめれば、
どこにも成長は生まれません。
だからこそ行動を起こすのです。
結果ではなく、行動を起こすことに意味があるからこそ
「ナイストライ」なのです。
アメリカ留学中にコーチの人達が、
成功には「グッドジャブ」
失敗には「ナイストライ」
と声をかけていました。
どちらもポジティブな言葉であり、考え方です。
結果に対して、
「怒る、教える、やらせる」の、
スリーパンチは行動を起こすことを躊躇させてしまいます。
日本のスポーツ界に必要な言葉、考え方は
「ナイストライ」であることを教えてくれました。
結果を恐れず行動を起こすこと。
そしてそのすべての結果を受け入れ、
次への成功へつなげること。
「ナイストライ」
とても心地よい響きのある、
そして前向きな気持ちにさせてくれる、
素晴らしい言葉だと思いませんか。
だから私のブログタイトルは、
ナイストライ!
なのです。
コーチングについて
2008年09月14日
久しぶりに週末自宅にいました。
2日間とも近所の多摩川河原で、
小学2年生になる長男と野球をしました。
「プロ野球のコーチが教えるから、上手になるでしょうね」
と、いつも羨ましがられます。
しかし、私はまったくと言っていいほど子供に技術を教えません。
ただひたすら、子供がやりたいように遊ばせています。
特にお気に入りなのが、試合です。
2人での試合ですから、ほとんどアウトが取れません。
延々と攻撃をしている子供は、
とても楽しそうにグランドを走り回っています。
何より楽しそうなのが、
スライディング(何も教えていないにもかかわらず)
をして服を汚すことです(笑)。
また攻撃をしているときは、
1番センター森本、2番セカンド田中賢介、3番稲葉・・・・・・
と選手の物まねを繰り返しています。
当然物まねをしているのですから、
それぞれの選手の特徴をよくつかんでいます。
また物まねをするには右打席、左打席、
両方で打つ必要がありますが、
まったく違和感なく打っています。
この年頃の子供にとって、
スイッチヒッターは教えてできるものではありません。
逆に教えないで、ただ見たままを形に表す物まねが、
可能にするのです。
教えることではなく、物まねが、
子供にとって最高の技術練習になっています。
これは子供達が、、
上手に右脳を使うことができることが大きな理由です。
教えた瞬間に左脳が働き、
体がうまく使えないのです。
楽しく、そして自ら工夫しながら遊ぶことが
上達への秘訣です。
また遊び始めたら、
「もう終わろう」と子供が飽きるまで、
付き合うことを心がけています。
プロ野球のコーチでも、野球経験ない父親でも、
子供に楽しさを感じさせることが、
上達を助けるのです。
楽しければ好きになり、
好きになれば上手になるのです。
そして何より、
子供との時間を共有する喜びが、
子供の楽しさにつながるのではないでしょうか。
楽しさ、見守り、共有、
これは私の子育ての根幹です。
コーチングの基本的な考え方ともいえます。
2日間とも近所の多摩川河原で、
小学2年生になる長男と野球をしました。
「プロ野球のコーチが教えるから、上手になるでしょうね」
と、いつも羨ましがられます。
しかし、私はまったくと言っていいほど子供に技術を教えません。
ただひたすら、子供がやりたいように遊ばせています。
特にお気に入りなのが、試合です。
2人での試合ですから、ほとんどアウトが取れません。
延々と攻撃をしている子供は、
とても楽しそうにグランドを走り回っています。
何より楽しそうなのが、
スライディング(何も教えていないにもかかわらず)
をして服を汚すことです(笑)。
また攻撃をしているときは、
1番センター森本、2番セカンド田中賢介、3番稲葉・・・・・・
と選手の物まねを繰り返しています。
当然物まねをしているのですから、
それぞれの選手の特徴をよくつかんでいます。
また物まねをするには右打席、左打席、
両方で打つ必要がありますが、
まったく違和感なく打っています。
この年頃の子供にとって、
スイッチヒッターは教えてできるものではありません。
逆に教えないで、ただ見たままを形に表す物まねが、
可能にするのです。
教えることではなく、物まねが、
子供にとって最高の技術練習になっています。
これは子供達が、、
上手に右脳を使うことができることが大きな理由です。
教えた瞬間に左脳が働き、
体がうまく使えないのです。
楽しく、そして自ら工夫しながら遊ぶことが
上達への秘訣です。
また遊び始めたら、
「もう終わろう」と子供が飽きるまで、
付き合うことを心がけています。
プロ野球のコーチでも、野球経験ない父親でも、
子供に楽しさを感じさせることが、
上達を助けるのです。
楽しければ好きになり、
好きになれば上手になるのです。
そして何より、
子供との時間を共有する喜びが、
子供の楽しさにつながるのではないでしょうか。
楽しさ、見守り、共有、
これは私の子育ての根幹です。
コーチングの基本的な考え方ともいえます。