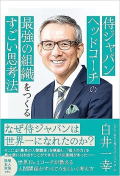コーチング
2013年07月29日
7月ももうすぐ終わりますね。
梅雨明けが早かったせいか、
今年の夏は暑さを感じますね。
また各地では集中豪雨などもあり、
気候の不安定さは心配材料ですね。
そんな夏を皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
明日から私はしばらく北海道滞在です。
毎日仕事が入っていますが、
それでもホテル生活や、
北海道の気候はバカンス気分を高めてくれますね(笑)。
美味しい食事も楽しみの一つですが、
自然に恵まれ、四季がはっきりとして、
北海道は本当に過ごしやすく、住みやすいところです。
将来的には住まいを北海道に移したいと思っています。
老後は夏は北海道、冬は生まれ故郷の香川で、
住み分けしながら、
全国各地で子供の野球の指導や、
指導者の支援をしたいと思っています。
私の長男も野球チームに入り、
夏休みに入ってから毎日のように練習や試合に出かけています。
昨日も練習のお手伝いをさせていただきましたが、
子供達の無限の可能性を引き出し、
開花させることは指導者の役割です。
年齢やレベルに応じて最も効果的な練習方法で、
必要な強度や量のバランスをとりながら、
何より怪我をしないこと、
そして野球への興味を膨らませることが大切です。
将来どうなりたいのか?
どのような選手になりたいのか?
なりたいと思った時点で、
そうなれる可能性が窮めて高くなる。
逆を言えばなりたい自分にしかなれないのですから、
子供たちが夢や目標を明確に、
具体的にしていくことが、
指導者として一番最初の重要な役目ですね。
体も心も鍛えるには、
猛練習は必要ですが、
それ以上に効果的に効率よく練習することのほうがもっと重要です。
指導者の役割とは選手の可能性を引き出し膨らませること、
指導者の成功とは選手が成功すること、
選手にとって有効な指導こそが指導です。
自分のやりたい指導、
独りよがりな指導、
根拠のない指導は指導とはいえませんね。
指導者らしい指導より、
選手にとってプラスになることこそが指導が求められます。
子供達の夢の実現、
可能性を最大限伸ばしていくような指導者が増えることを望んでいます。
私も将来は直接子供の指導に係ったり、
指導者の指導、育成、支援をしていくことが私の老後の楽しみです。
子供達の無限の可能性に係われる事は、
とても魅力的ですし、責任重大ですね。
昨日は子供達の練習のお手伝いをさせていただき、
改めて指導者としての喜びを感じることが出来ました。
梅雨明けが早かったせいか、
今年の夏は暑さを感じますね。
また各地では集中豪雨などもあり、
気候の不安定さは心配材料ですね。
そんな夏を皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
明日から私はしばらく北海道滞在です。
毎日仕事が入っていますが、
それでもホテル生活や、
北海道の気候はバカンス気分を高めてくれますね(笑)。
美味しい食事も楽しみの一つですが、
自然に恵まれ、四季がはっきりとして、
北海道は本当に過ごしやすく、住みやすいところです。
将来的には住まいを北海道に移したいと思っています。
老後は夏は北海道、冬は生まれ故郷の香川で、
住み分けしながら、
全国各地で子供の野球の指導や、
指導者の支援をしたいと思っています。
私の長男も野球チームに入り、
夏休みに入ってから毎日のように練習や試合に出かけています。
昨日も練習のお手伝いをさせていただきましたが、
子供達の無限の可能性を引き出し、
開花させることは指導者の役割です。
年齢やレベルに応じて最も効果的な練習方法で、
必要な強度や量のバランスをとりながら、
何より怪我をしないこと、
そして野球への興味を膨らませることが大切です。
将来どうなりたいのか?
どのような選手になりたいのか?
なりたいと思った時点で、
そうなれる可能性が窮めて高くなる。
逆を言えばなりたい自分にしかなれないのですから、
子供たちが夢や目標を明確に、
具体的にしていくことが、
指導者として一番最初の重要な役目ですね。
体も心も鍛えるには、
猛練習は必要ですが、
それ以上に効果的に効率よく練習することのほうがもっと重要です。
指導者の役割とは選手の可能性を引き出し膨らませること、
指導者の成功とは選手が成功すること、
選手にとって有効な指導こそが指導です。
自分のやりたい指導、
独りよがりな指導、
根拠のない指導は指導とはいえませんね。
指導者らしい指導より、
選手にとってプラスになることこそが指導が求められます。
子供達の夢の実現、
可能性を最大限伸ばしていくような指導者が増えることを望んでいます。
私も将来は直接子供の指導に係ったり、
指導者の指導、育成、支援をしていくことが私の老後の楽しみです。
子供達の無限の可能性に係われる事は、
とても魅力的ですし、責任重大ですね。
昨日は子供達の練習のお手伝いをさせていただき、
改めて指導者としての喜びを感じることが出来ました。
コーチング
2013年07月23日
今日は休養日です。
午前中に砧公園でじっくりウォークトレーニングして、
これから少し遅めのランチに出かけます。
私は今年は野球解説や講演を中心に活動しています。
講演の中では、
チームビルディング、コーチング、コミュニケーションスキル、
メンタルトレーニングなどがメインテーマです。
とくに選手育成にはビジネスコーチングを取り入れ、
スポーツ界の主流である指示命令恫喝、体罰などを使った指導ではなく、
選手がやる気に満ち溢れ、
自ら行動を起こし、
目指すべきゴールに到達できるように、
サポートすることに徹する指導方法をテーマに講演しています。
そんなこともあり講演を受講した方々から、
パーソナルコーチの依頼が来るようになりました。
私の場合は、
コーチングやメンタルなどを取り入れながら、
メンター的要素が強いかかわり方で、
パーソナルアドバイザーをしてきた経験があります。
今後のことはまだ検討中ではありますが、
前向きに考えていることも事実です。
なぜならコーチは、
コーチングをしながら、
自らの学びや気づきも多いからです。
クライアントの為にも、
そして自分自身の為にも、
プラスになることばかりです。
私も実は、
最近自分自身をコーチしています。
それはゴルフの話ですが、
将来のエージシューターを目指して、
フォームの再構築をしています。
私の通っている代々木公園のジムにあるゴルフレンジに、
新しく映像解析装置が導入されました。
正面と後方からのカメラで映像を撮り、
それを2画面で直ちに確認することが出来ます。
当然スローにしたりコマ送りにしたり、
ラインなどの書き込みも出来ます。
私は元々ゴルフが大好きで、
フォームにもある程度自信を持っていましたが、
この映像解析装置を初めて使ったときに、
自分の考えているフォームと、
実際に打っているフォームの違いに愕然としました。
イメージと現実の違い、
自分を自分で見るには映像しかありません。
野球では映像を使っての指導をしてきましたが、
自分のゴルフを映像で見る機会がなかったので、
イメージと現実のギャップの大きさには驚きました。
将来エイジシュートを達成するためには、
フォームの再構築の重要性を感じ、
時間を見つけてはジムに通い、
映像確認しながら、
自分自身をコーチしています。
相手をコーチすることは本職ですが、
自分をコーチするのは初めてです(笑)。
なかなか優等生のクライアントですから、
コーチの指導に対する反応もよく、
言葉と映像を使っての具体的指導なので、
上達も早いです(笑)。
最近のゴルフでの好スコアは、
コーチのおかげだと思っています。
セルフトーク、セルフカウンセリング、セルフコーチ、
自分自身とかかわりは、
何よりも重要ですね。
皆さんも自分自身にとって、
最高のコーチとなり、
自分自身を成功に導いてくださいね。
午前中に砧公園でじっくりウォークトレーニングして、
これから少し遅めのランチに出かけます。
私は今年は野球解説や講演を中心に活動しています。
講演の中では、
チームビルディング、コーチング、コミュニケーションスキル、
メンタルトレーニングなどがメインテーマです。
とくに選手育成にはビジネスコーチングを取り入れ、
スポーツ界の主流である指示命令恫喝、体罰などを使った指導ではなく、
選手がやる気に満ち溢れ、
自ら行動を起こし、
目指すべきゴールに到達できるように、
サポートすることに徹する指導方法をテーマに講演しています。
そんなこともあり講演を受講した方々から、
パーソナルコーチの依頼が来るようになりました。
私の場合は、
コーチングやメンタルなどを取り入れながら、
メンター的要素が強いかかわり方で、
パーソナルアドバイザーをしてきた経験があります。
今後のことはまだ検討中ではありますが、
前向きに考えていることも事実です。
なぜならコーチは、
コーチングをしながら、
自らの学びや気づきも多いからです。
クライアントの為にも、
そして自分自身の為にも、
プラスになることばかりです。
私も実は、
最近自分自身をコーチしています。
それはゴルフの話ですが、
将来のエージシューターを目指して、
フォームの再構築をしています。
私の通っている代々木公園のジムにあるゴルフレンジに、
新しく映像解析装置が導入されました。
正面と後方からのカメラで映像を撮り、
それを2画面で直ちに確認することが出来ます。
当然スローにしたりコマ送りにしたり、
ラインなどの書き込みも出来ます。
私は元々ゴルフが大好きで、
フォームにもある程度自信を持っていましたが、
この映像解析装置を初めて使ったときに、
自分の考えているフォームと、
実際に打っているフォームの違いに愕然としました。
イメージと現実の違い、
自分を自分で見るには映像しかありません。
野球では映像を使っての指導をしてきましたが、
自分のゴルフを映像で見る機会がなかったので、
イメージと現実のギャップの大きさには驚きました。
将来エイジシュートを達成するためには、
フォームの再構築の重要性を感じ、
時間を見つけてはジムに通い、
映像確認しながら、
自分自身をコーチしています。
相手をコーチすることは本職ですが、
自分をコーチするのは初めてです(笑)。
なかなか優等生のクライアントですから、
コーチの指導に対する反応もよく、
言葉と映像を使っての具体的指導なので、
上達も早いです(笑)。
最近のゴルフでの好スコアは、
コーチのおかげだと思っています。
セルフトーク、セルフカウンセリング、セルフコーチ、
自分自身とかかわりは、
何よりも重要ですね。
皆さんも自分自身にとって、
最高のコーチとなり、
自分自身を成功に導いてくださいね。
コーチング
2010年04月20日
昨日ゆっくりし過ぎたのか、
今朝から咳が出て喉も痛くなりました。
たまの休日で気が緩んだのか、
それともトライアスロンの練習で疲労がたまっていたのか、
身体が休めとサインを送ってきているようです。
またはほとんど自分でやっていない布団干しをしたので、
布団が喜んで私を呼び込んだのか(笑)、
何もしないで一日中静養しました。
食欲もなかったので、
動物と同じように食事もとらずにいます。
野生動物は体調不良になると断食をして体(内臓)を休め、
免疫力を回復すると言われています。
今日は動物的静養で、体調回復に努めています(笑)。
たまたま今日もスケジュールが空いていましたので助かりました。
その分今日は読みたかった本を読むことが出来ました。
普段は移動時間を利用して本を読むのですが、
今日はまとまった時間を読書に充てました。
その中の一冊で、皆さんにお勧めしたい本があります。
それが石川尚子さんのコーチング本、
「コーチングのとびら」です。
私もこの本の帯に推薦文を書かせていただいていますが、
まさにコーチの中のコーチ、石川尚子さんの書いた本です。
たくさん出版されているコーチング本の中でも、
とても解りやすく、すぐに実践したくなる内容です。
機会があればぜひ読んでいただき、
コーチングを身近に感じていただければと思います。
何度読んでもヒント、気づき与えてくれる本です。
さて今日からバッファローズ戦ですが、
前回好投の増井投手に期待ですね。
今夜は休養万全で応援します。
今朝から咳が出て喉も痛くなりました。
たまの休日で気が緩んだのか、
それともトライアスロンの練習で疲労がたまっていたのか、
身体が休めとサインを送ってきているようです。
またはほとんど自分でやっていない布団干しをしたので、
布団が喜んで私を呼び込んだのか(笑)、
何もしないで一日中静養しました。
食欲もなかったので、
動物と同じように食事もとらずにいます。
野生動物は体調不良になると断食をして体(内臓)を休め、
免疫力を回復すると言われています。
今日は動物的静養で、体調回復に努めています(笑)。
たまたま今日もスケジュールが空いていましたので助かりました。
その分今日は読みたかった本を読むことが出来ました。
普段は移動時間を利用して本を読むのですが、
今日はまとまった時間を読書に充てました。
その中の一冊で、皆さんにお勧めしたい本があります。
それが石川尚子さんのコーチング本、
「コーチングのとびら」です。
私もこの本の帯に推薦文を書かせていただいていますが、
まさにコーチの中のコーチ、石川尚子さんの書いた本です。
たくさん出版されているコーチング本の中でも、
とても解りやすく、すぐに実践したくなる内容です。
機会があればぜひ読んでいただき、
コーチングを身近に感じていただければと思います。
何度読んでもヒント、気づき与えてくれる本です。
さて今日からバッファローズ戦ですが、
前回好投の増井投手に期待ですね。
今夜は休養万全で応援します。
コーチング
2010年03月14日
昨日は旭川で講演でした。
人材育成をテーマにした内容ですが、
モデルケースになっているのがファイターズにおける選手育成です。
2001年以降のファイターズの選手育成には、
コーチングを導入して成果を挙げました。
しかし、私達はコーチングのことをまったく知らずに、
「選手のモチベーションを上げるためにはどのような指導方法が必要なのか」
を考えながら指導方法を変えました。
「伸びる選手はやる気に満ち溢れ、自らが前向きに取り組み練習しする」
のですから、
我々指導者の取り組むべき方向性は、
選手のやる気を引き出し、大きく育て、
選手自らが取り組める環境づくりをすることでした。
そのための取り組みの一つがコーチングだったわけです。
選手の意識が変わり、取り組みが変わり、
順調に成果が上がってきた頃にコーチングを知りました。
2002年に改めてファームすべての指導者がコーチングの研修を受けました。
これまで取り組んでいた指導方法がコーチングそのものだったにもかかわらず、
コーチングの研修を受けたことでかえってぎこちないものになった時期がありました。
コーチングのスキルを学んだことで、
忠実にスキルを実行することに意識をとられたことが原因でした。
コーチングを学ぶことも、スキルを習得することも大切ですが、
何よりも大切なことはコーチングマインドだった訳です。
コーチング研修を受けた方から、
「コーチングは難しいのですが」と質問されることがあります。
スキルに意識をとられることや、
コーチングそのものに疑問を抱きながらでは成果は上がらないように思います。
相手のモチベーションを上げるには、
自分のモチベーションを上げることであり、
なにより相手の成長を願う強い気持ちが必要です。
知らなくてもできているコーチング、
学んでもできないコーチングということを私達も体験しました。
知識、スキル以上に大切なのは、
想いではないでしょうか。
自らがいつも前向きに、
やる気、元気に満ち溢れ、
楽しみながら全力で取り組んでいれば、
それ自体が「相手の気づき」となり、
コーチングになっているように思います。
自分の中でコーチングマインドを育て、
自分自身にコーチングをすることが秘訣のように思います。
人材育成をテーマにした内容ですが、
モデルケースになっているのがファイターズにおける選手育成です。
2001年以降のファイターズの選手育成には、
コーチングを導入して成果を挙げました。
しかし、私達はコーチングのことをまったく知らずに、
「選手のモチベーションを上げるためにはどのような指導方法が必要なのか」
を考えながら指導方法を変えました。
「伸びる選手はやる気に満ち溢れ、自らが前向きに取り組み練習しする」
のですから、
我々指導者の取り組むべき方向性は、
選手のやる気を引き出し、大きく育て、
選手自らが取り組める環境づくりをすることでした。
そのための取り組みの一つがコーチングだったわけです。
選手の意識が変わり、取り組みが変わり、
順調に成果が上がってきた頃にコーチングを知りました。
2002年に改めてファームすべての指導者がコーチングの研修を受けました。
これまで取り組んでいた指導方法がコーチングそのものだったにもかかわらず、
コーチングの研修を受けたことでかえってぎこちないものになった時期がありました。
コーチングのスキルを学んだことで、
忠実にスキルを実行することに意識をとられたことが原因でした。
コーチングを学ぶことも、スキルを習得することも大切ですが、
何よりも大切なことはコーチングマインドだった訳です。
コーチング研修を受けた方から、
「コーチングは難しいのですが」と質問されることがあります。
スキルに意識をとられることや、
コーチングそのものに疑問を抱きながらでは成果は上がらないように思います。
相手のモチベーションを上げるには、
自分のモチベーションを上げることであり、
なにより相手の成長を願う強い気持ちが必要です。
知らなくてもできているコーチング、
学んでもできないコーチングということを私達も体験しました。
知識、スキル以上に大切なのは、
想いではないでしょうか。
自らがいつも前向きに、
やる気、元気に満ち溢れ、
楽しみながら全力で取り組んでいれば、
それ自体が「相手の気づき」となり、
コーチングになっているように思います。
自分の中でコーチングマインドを育て、
自分自身にコーチングをすることが秘訣のように思います。
コーチング
2010年02月26日
今日は午後から札幌市内で講演です。
コーチングによる人材育成がテーマです。
今年もいろんなところで講演させていただいていますが、
講演をするたびに自分自身が一番勉強になっているように感じます。
人前で話すると毎回のように気づきがあり、
そして責任感が出てきます。
コーチングでも質問し、そして聞くことが重要と言われますが、
一番気づきの多いのは話をしている側ですから、
指導者としてはたくさん選手の話を引き出すことが大切です。
選手が話をすればするほど気づきが生まれ、
そして責任を持つようになるので、
自然と成長していくのです。
キャンプでも選手の状態を見て、
順調に推移している選手と、
試行錯誤を繰り返しながら問題解決できていない選手が目に付きました。
そして試行錯誤の方向性が間違えている選手に対しても、
残念ながらアドバイスはできません。
選手の試行錯誤を繰り返している段階は、
まさしく聞く準備のできていない状態です。
聞く準備のできていないときには、
どのようなアドバイスでもプラスにはなりません。
どのタイミングでアドバイスをするのかは、
どんなアドバイスをするよりも重要な場合があります。
選手が聞く準備ができているのは、
選手自身が質問してきたときです。
このときにアドバイスするよりも、
選手が聞きたいこと思っていることををどんどん引き出していけば、
話をしながら選手自身が気づいていくものです。
選手にとっては教えられるよりも、
自分自身の気づきのほうがより大きな力になります。
指導者は教えるのが仕事のように考えがちですが、
指導者は選手の気づきを引き出すことが仕事です。
指導者が教えるという既成概念に捉われながら指導者らしい仕事をするよりも、
教えない指導者は既成概念からいえば指導者らしくありませんが、
選手にとってプラスになることが多いのです。
またアドバイスをする場合でも、
一方的に「これだ」とアドバイスをするよりも、
「これとこれだったらどちらを選択する?」
といくつか提示しながら質問することです。
そして選手自らが選択することで、
一方的なアドバイスではなくなります。
あくまでも選手自身の選択が大切なのです。
タイミングを待ちながら、
選手の試行錯誤を見守りながら、
答えの準備をしていくことが指導者の仕事です。
教えないで待つこと、
そしてじっくりと準備をすることは指導者としては難しいものです。
待っている間は何もしない指導者と言われかねませんから。
既成概念に捉われずに、
選手にとって本当にプラスになれる、
選手の成功をサポートできる指導者でありたいですね。
コーチングによる人材育成がテーマです。
今年もいろんなところで講演させていただいていますが、
講演をするたびに自分自身が一番勉強になっているように感じます。
人前で話すると毎回のように気づきがあり、
そして責任感が出てきます。
コーチングでも質問し、そして聞くことが重要と言われますが、
一番気づきの多いのは話をしている側ですから、
指導者としてはたくさん選手の話を引き出すことが大切です。
選手が話をすればするほど気づきが生まれ、
そして責任を持つようになるので、
自然と成長していくのです。
キャンプでも選手の状態を見て、
順調に推移している選手と、
試行錯誤を繰り返しながら問題解決できていない選手が目に付きました。
そして試行錯誤の方向性が間違えている選手に対しても、
残念ながらアドバイスはできません。
選手の試行錯誤を繰り返している段階は、
まさしく聞く準備のできていない状態です。
聞く準備のできていないときには、
どのようなアドバイスでもプラスにはなりません。
どのタイミングでアドバイスをするのかは、
どんなアドバイスをするよりも重要な場合があります。
選手が聞く準備ができているのは、
選手自身が質問してきたときです。
このときにアドバイスするよりも、
選手が聞きたいこと思っていることををどんどん引き出していけば、
話をしながら選手自身が気づいていくものです。
選手にとっては教えられるよりも、
自分自身の気づきのほうがより大きな力になります。
指導者は教えるのが仕事のように考えがちですが、
指導者は選手の気づきを引き出すことが仕事です。
指導者が教えるという既成概念に捉われながら指導者らしい仕事をするよりも、
教えない指導者は既成概念からいえば指導者らしくありませんが、
選手にとってプラスになることが多いのです。
またアドバイスをする場合でも、
一方的に「これだ」とアドバイスをするよりも、
「これとこれだったらどちらを選択する?」
といくつか提示しながら質問することです。
そして選手自らが選択することで、
一方的なアドバイスではなくなります。
あくまでも選手自身の選択が大切なのです。
タイミングを待ちながら、
選手の試行錯誤を見守りながら、
答えの準備をしていくことが指導者の仕事です。
教えないで待つこと、
そしてじっくりと準備をすることは指導者としては難しいものです。
待っている間は何もしない指導者と言われかねませんから。
既成概念に捉われずに、
選手にとって本当にプラスになれる、
選手の成功をサポートできる指導者でありたいですね。
コーチング
2010年01月23日
コーチングのことは多くの方が認識していると思います。
相手の可能性を引き出し、サポートすること。
傾聴や承認などの要素の必要性はよく言われていることです。
反対に「叱る」「厳しい」とは、
かけ離れている印象を持っている方が多いと思います。
コーチングセミナーでは、
叱り方や厳しさの必要性を教えてくれるところはあるのでしょうか?
叱ってはいけないとか、
厳しさはコーチング敵とでも思っている方が圧倒的に多いのではないでしょうか?
その一方で最近は叱れない親、先生、上司、
指導者が問題になるケースも多くなっています。
私はコーチングの理論やテクニックの重要性を感じますが、
それ以上にコーチングマインドが必要だと思います。
相手の可能性を信じ、全力を尽くしサポートするとには、
深い愛情や想いを持ち、
ある時には徹底して「叱る」ことや「厳しさ」も、
必要不可欠だとも思っています。
私も選手時代には多くの指導者に指導を受けました。
高校や大学時代を振り返ってみると、
毎日のように叱られ、厳しさを感じていました。
しかし、どれだけ叱られても、どれだけ厳しくされても、
反発したり、憎くらしく思ったりしたことは一度もありませんでした。
そこには深い愛情が感じられたからだと思っています。
叱ってばかりいても、
どれだけ厳しくしていてもコーチングのできている指導者は案外多いのです。
叱り上手は愛情の裏返し、
厳しさは愛情の裏返し、
感情ではなく愛情を持って叱り、
厳しく接することも相手の可能性を引き出し、
サポートすることにつながると思います。
優しいけれど、テクニックはあるけれどもコーチングのできないコーチ、
厳しいけれど、叱っているけれどもコーチングのできているコーチがいるのも事実です。
「叱っても叱っても同じミスを繰り返す」のは、
叱られる側の問題だけでなく、
叱る側にも問題があるのではないでしょうか。
叱るからには、二度と同じ過ちを犯さないように、
身に染みるまで徹底して叱るべきです。
深い愛情、想いがあり、
沈着冷静さと燃え上がるような情熱を持ち備えたうえに、
コーチングの理論やテクニックを理解できてこそ、
本当のコーチと言えるでしょう。
怒るは感情、叱るは愛情。
優しく、楽しいけれども厳しい指導者。
褒め上手であり叱り上手。
相手の成功を自分のこと以上に喜び、
深い愛情と想いをこめて、厳しく叱かることもできる、
そんな指導者でありたいですね。
相手の可能性を引き出し、サポートすること。
傾聴や承認などの要素の必要性はよく言われていることです。
反対に「叱る」「厳しい」とは、
かけ離れている印象を持っている方が多いと思います。
コーチングセミナーでは、
叱り方や厳しさの必要性を教えてくれるところはあるのでしょうか?
叱ってはいけないとか、
厳しさはコーチング敵とでも思っている方が圧倒的に多いのではないでしょうか?
その一方で最近は叱れない親、先生、上司、
指導者が問題になるケースも多くなっています。
私はコーチングの理論やテクニックの重要性を感じますが、
それ以上にコーチングマインドが必要だと思います。
相手の可能性を信じ、全力を尽くしサポートするとには、
深い愛情や想いを持ち、
ある時には徹底して「叱る」ことや「厳しさ」も、
必要不可欠だとも思っています。
私も選手時代には多くの指導者に指導を受けました。
高校や大学時代を振り返ってみると、
毎日のように叱られ、厳しさを感じていました。
しかし、どれだけ叱られても、どれだけ厳しくされても、
反発したり、憎くらしく思ったりしたことは一度もありませんでした。
そこには深い愛情が感じられたからだと思っています。
叱ってばかりいても、
どれだけ厳しくしていてもコーチングのできている指導者は案外多いのです。
叱り上手は愛情の裏返し、
厳しさは愛情の裏返し、
感情ではなく愛情を持って叱り、
厳しく接することも相手の可能性を引き出し、
サポートすることにつながると思います。
優しいけれど、テクニックはあるけれどもコーチングのできないコーチ、
厳しいけれど、叱っているけれどもコーチングのできているコーチがいるのも事実です。
「叱っても叱っても同じミスを繰り返す」のは、
叱られる側の問題だけでなく、
叱る側にも問題があるのではないでしょうか。
叱るからには、二度と同じ過ちを犯さないように、
身に染みるまで徹底して叱るべきです。
深い愛情、想いがあり、
沈着冷静さと燃え上がるような情熱を持ち備えたうえに、
コーチングの理論やテクニックを理解できてこそ、
本当のコーチと言えるでしょう。
怒るは感情、叱るは愛情。
優しく、楽しいけれども厳しい指導者。
褒め上手であり叱り上手。
相手の成功を自分のこと以上に喜び、
深い愛情と想いをこめて、厳しく叱かることもできる、
そんな指導者でありたいですね。
コーチング
2009年11月29日
週末は長野で野球教室でした。
先週も週末は福島でしたので、
毎週のように週末は長距離ドライブをしています。
週末は高速道路1,000円になったことで、
毎週大渋滞が続いているので、
想像以上の長時間のドライブになります。
今回は長男も同伴して、
野球教室に一緒に参加することができたので、
長時間のドライブも大切なコミュニケーションの場となりました。
今日の野球教室は幼稚園児から、
小学6年生まで幅広い年齢でした。
私が引き受けたのは幼稚園児から小学4年生までの子供達でした。
投げ方や捕り方を教えるのではなく、
自由に投げ、自由に捕らせました。
ただ一つ早く投げ返すことだけをルールに、
一人5球連続でボールを追わせ、
そして捕球し投げ返すことを繰り返すだけの練習です。
私がゴロやフライをランダムに投げ、
子供たちはただ必死にボールを捕り、
投げ返すことを繰り返すことに集中している間に、
正確に捕球し、そして送球できるようになるのです。
自然にバックハンドやショートバウンドの捕球、
スナップを使ったやわらかい送球まででき、
そして何より積極的に取り組むようになるのです。
「もっと、もっと」といつまでも練習するようになり、
苦手な守備練習も大好きになってしまいます。
捕り方や投げ方にまったく規制をかけずに、
ただ素早く、連続することで、
難しい捕り方や投げ方まで自然にできるようになるのは、
技術を教えないからです。
運動会で球入れ競争をする時に、
投げ方を説明する先生はいませんが、
何球も籠に球が入ります。
子供にみかんを投げると、
誰でも両手で大切に捕ります。
教えなくても本能で、
無意識にできるのですから、
教える必要はないのです。
少し取り組み方を代えるだけで、
子供たちは才能を総動員させながら、
楽しく練習ができるのです。
楽しい=大好きであり、
大好きになれば上達するのではないでしょうか。
小学低学年までの練習は、
いかに楽しく熱中できるような方法を取り入れるかが大切です。
指導者は教えるのではなく、
楽しい練習方法を用意することが役割です。
子供の限りない可能性を引き出すには、
まずは楽しませること、
大好きにしてあげることです。
今日は子供達を楽しませようとしたことで、
一番楽しんでいたのは私でした(笑)。
人を楽しませるには、自分自身が楽しむことです。
怒声、罵声を浴びせるのではなく、
子供を楽しませ、夢中にさせる指導者が増えることを願っています。
先週も週末は福島でしたので、
毎週のように週末は長距離ドライブをしています。
週末は高速道路1,000円になったことで、
毎週大渋滞が続いているので、
想像以上の長時間のドライブになります。
今回は長男も同伴して、
野球教室に一緒に参加することができたので、
長時間のドライブも大切なコミュニケーションの場となりました。
今日の野球教室は幼稚園児から、
小学6年生まで幅広い年齢でした。
私が引き受けたのは幼稚園児から小学4年生までの子供達でした。
投げ方や捕り方を教えるのではなく、
自由に投げ、自由に捕らせました。
ただ一つ早く投げ返すことだけをルールに、
一人5球連続でボールを追わせ、
そして捕球し投げ返すことを繰り返すだけの練習です。
私がゴロやフライをランダムに投げ、
子供たちはただ必死にボールを捕り、
投げ返すことを繰り返すことに集中している間に、
正確に捕球し、そして送球できるようになるのです。
自然にバックハンドやショートバウンドの捕球、
スナップを使ったやわらかい送球まででき、
そして何より積極的に取り組むようになるのです。
「もっと、もっと」といつまでも練習するようになり、
苦手な守備練習も大好きになってしまいます。
捕り方や投げ方にまったく規制をかけずに、
ただ素早く、連続することで、
難しい捕り方や投げ方まで自然にできるようになるのは、
技術を教えないからです。
運動会で球入れ競争をする時に、
投げ方を説明する先生はいませんが、
何球も籠に球が入ります。
子供にみかんを投げると、
誰でも両手で大切に捕ります。
教えなくても本能で、
無意識にできるのですから、
教える必要はないのです。
少し取り組み方を代えるだけで、
子供たちは才能を総動員させながら、
楽しく練習ができるのです。
楽しい=大好きであり、
大好きになれば上達するのではないでしょうか。
小学低学年までの練習は、
いかに楽しく熱中できるような方法を取り入れるかが大切です。
指導者は教えるのではなく、
楽しい練習方法を用意することが役割です。
子供の限りない可能性を引き出すには、
まずは楽しませること、
大好きにしてあげることです。
今日は子供達を楽しませようとしたことで、
一番楽しんでいたのは私でした(笑)。
人を楽しませるには、自分自身が楽しむことです。
怒声、罵声を浴びせるのではなく、
子供を楽しませ、夢中にさせる指導者が増えることを願っています。
コーチング
2009年10月04日
ファイターズはマジック1としました。
今日もワンチャンスで、
ファイターズらしいつなぎの野球で逆転勝利。
明日はSTVテレビで解説が入っていますので、
優勝決定の試合に立ち会えそうです。
現在の主力はファーム監督時代からの選手も多く、
ルーキーだった頃を懐かしく思い出します。
子供のようだった選手達がたくましく成長を遂げ、
今では本当に頼もしく感じます。
輝いている選手たちの活躍に期待しながら、
明日の解説楽しみしています。
さて今日はコーチングについて講演させていただきました。
講演内容は、
2001年から始めたファイターズファームにおける選手育成、
指導方法についての話でした。
指示、命令、恫喝、
怒り、教え、やらせるることで、
指導者が一生懸命「選手の身体を動かす」従来型の指導方法からの脱却。
やる気や向上心を引き出し、大きく膨らませることで、
選手自ら考え、行動し、そして積極的に伸び伸びとプレーできる環境作り。
身体ではなく、やる気や向上心などの、
選手の「心を動かす」指導方法についての話でした。
コーチングを勉強して取り組み始めたのではなく、
取り組み始めた指導方法の一つがコーチングだったので、
理論より実践が先でした。
私が指導する上で大切にしていたのがメンタル、
選手の心の動きに対してアプローチしていたことが、
コーチングそのものだったと言う事です。
これは選手時代にメンタルトレーニングに取り組んでいたことが、
大きく影響しています。
メンタルトレーニングが、結果的にはコーチングにつながったことで
2007年に出版した著書「メンタルコーチング」のネーミングになったのです。
この本がきっかけで、
沢山の講演依頼をいただけるようになり、
そして今でもこの本の内容を中心に、
話をさせていただいています。
特に今日の講演会参加の皆さんは、
よくコーチングを勉強し、実践している方ばかりでしたので、
会場のエネルギーが素晴らしかったです。
パネルディスカッションや質疑応答、懇親会など、
長時間ご一緒させていただきましたが、
私のほうが勉強になることばかりで、
心躍るような一日でした。
コーチングマインド持っている皆さんのパワーは、
みんなを元気にしてくれますね。
今日も沢山の素晴らしい出会いに感謝、感激です。
今日もワンチャンスで、
ファイターズらしいつなぎの野球で逆転勝利。
明日はSTVテレビで解説が入っていますので、
優勝決定の試合に立ち会えそうです。
現在の主力はファーム監督時代からの選手も多く、
ルーキーだった頃を懐かしく思い出します。
子供のようだった選手達がたくましく成長を遂げ、
今では本当に頼もしく感じます。
輝いている選手たちの活躍に期待しながら、
明日の解説楽しみしています。
さて今日はコーチングについて講演させていただきました。
講演内容は、
2001年から始めたファイターズファームにおける選手育成、
指導方法についての話でした。
指示、命令、恫喝、
怒り、教え、やらせるることで、
指導者が一生懸命「選手の身体を動かす」従来型の指導方法からの脱却。
やる気や向上心を引き出し、大きく膨らませることで、
選手自ら考え、行動し、そして積極的に伸び伸びとプレーできる環境作り。
身体ではなく、やる気や向上心などの、
選手の「心を動かす」指導方法についての話でした。
コーチングを勉強して取り組み始めたのではなく、
取り組み始めた指導方法の一つがコーチングだったので、
理論より実践が先でした。
私が指導する上で大切にしていたのがメンタル、
選手の心の動きに対してアプローチしていたことが、
コーチングそのものだったと言う事です。
これは選手時代にメンタルトレーニングに取り組んでいたことが、
大きく影響しています。
メンタルトレーニングが、結果的にはコーチングにつながったことで
2007年に出版した著書「メンタルコーチング」のネーミングになったのです。
この本がきっかけで、
沢山の講演依頼をいただけるようになり、
そして今でもこの本の内容を中心に、
話をさせていただいています。
特に今日の講演会参加の皆さんは、
よくコーチングを勉強し、実践している方ばかりでしたので、
会場のエネルギーが素晴らしかったです。
パネルディスカッションや質疑応答、懇親会など、
長時間ご一緒させていただきましたが、
私のほうが勉強になることばかりで、
心躍るような一日でした。
コーチングマインド持っている皆さんのパワーは、
みんなを元気にしてくれますね。
今日も沢山の素晴らしい出会いに感謝、感激です。