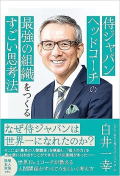練習の目的
2014年10月30日
練習量が少ないと心配でしょうか?
練習量が多いと安心でしょうか?
練習の目的は、
体力、技術、メンタルを含めた、
能力の向上でですね。
練習とは質の高さであり、
その中に、
練習強度や量の問題が含まれます。
成果の上がる質の高い練習とは、
正しい方向性で、
効果的な方法で、
尚且つ強度と量のバランスが取れ、
明確な目的意識を持ち、
集中して取り組むことです。
特に方向性は重要ですね。
各チームにより、
秋季キャンプの位置付けは異なります。
ファイターズでも昨年と今年では、
チームの変化に合わせて
当然のように変化しますが、
目指す方向性は変わりません。
それは来シーズンに向けて、
十分な成果をあげる事です。
チームの方向性、
各選手の方向性を明確にし、
ゴールに向かって進むだけです。
方向性がズレてしまえば、
いくら頑張って練習しても
ゴールには到達しません。
そして方向性が正しくても、
方法が間違えばどうなるでしょうか?
効率が悪いですね。
また方法が正しくても、
強度と量のバランスが悪ければ、
怪我のリスクが高まり、
効果が半減します。
たとえば、
ダッシュやジャンプは強度が高く、
量が多くなり過ぎると
怪我につながります。
反対に技術練習は、
正しい動きで何度も反復しないと
身につきません。
また正しい動きができない時に
反復練習すれば悪い癖がつきます。
同じ技術練習、
反復練習でもタイミングは必要です。
練習の目的に応じて、
強度や量のバランスが整わなければ、
成果は上がりません。
反対に強度が弱くや量が少なくても、
質の高い練習は可能です。
シーズンの疲れを抜く為に、
リカバリーを目的にすれば、
強度は低い方が良く、
量も少ない方が良いですね。
練習とは目的に応じて、
いろんな要素がありますので、
量=向上ではありません。
当然量が必要な時には、
量を求めますし、
猛練習もしますが、
あくまでも必要に応じてです。
練習量について
理解いただけたでしょうか?
練習量が多いと安心でしょうか?
練習の目的は、
体力、技術、メンタルを含めた、
能力の向上でですね。
練習とは質の高さであり、
その中に、
練習強度や量の問題が含まれます。
成果の上がる質の高い練習とは、
正しい方向性で、
効果的な方法で、
尚且つ強度と量のバランスが取れ、
明確な目的意識を持ち、
集中して取り組むことです。
特に方向性は重要ですね。
各チームにより、
秋季キャンプの位置付けは異なります。
ファイターズでも昨年と今年では、
チームの変化に合わせて
当然のように変化しますが、
目指す方向性は変わりません。
それは来シーズンに向けて、
十分な成果をあげる事です。
チームの方向性、
各選手の方向性を明確にし、
ゴールに向かって進むだけです。
方向性がズレてしまえば、
いくら頑張って練習しても
ゴールには到達しません。
そして方向性が正しくても、
方法が間違えばどうなるでしょうか?
効率が悪いですね。
また方法が正しくても、
強度と量のバランスが悪ければ、
怪我のリスクが高まり、
効果が半減します。
たとえば、
ダッシュやジャンプは強度が高く、
量が多くなり過ぎると
怪我につながります。
反対に技術練習は、
正しい動きで何度も反復しないと
身につきません。
また正しい動きができない時に
反復練習すれば悪い癖がつきます。
同じ技術練習、
反復練習でもタイミングは必要です。
練習の目的に応じて、
強度や量のバランスが整わなければ、
成果は上がりません。
反対に強度が弱くや量が少なくても、
質の高い練習は可能です。
シーズンの疲れを抜く為に、
リカバリーを目的にすれば、
強度は低い方が良く、
量も少ない方が良いですね。
練習とは目的に応じて、
いろんな要素がありますので、
量=向上ではありません。
当然量が必要な時には、
量を求めますし、
猛練習もしますが、
あくまでも必要に応じてです。
練習量について
理解いただけたでしょうか?
質問にお答えします
2013年11月19日
飯田の山さん。
昨日は雄で、
美味しい料理をたくさんいただきました。
フグも神戸牛も、
明石のタコに渡り蟹、
満喫しました。
しかしゴルフは、
名門廣野ゴルフ倶楽部に、
完璧に跳ね返されてしまいました。
何度挑戦しても未熟さを教えてくれます。
その一方で今度こそと、
ファイトが湧き上がります。
来年はぜひとも雄&廣野ゴルフ倶楽部、
ご一緒しましょう。
みよさん。
来月の室蘭は練成会の研修ですので、
残念ながら一般公開ではありません。
またの機会によろしくお願いします。
日本ネコさん。
来年は神戸での試合では、
必ず雄で食事をしますので、
お会い出来れば良いですね。
楽しみにしています。
今は新幹線で東京に向かっています。
明日もスケジュールが空いていますので、
たまっている雑用を片付けて、
明後日からの過密スケジュールへの準備です。
ウォークトレーニングもできていないので、
砧公園でしっかり身体を動かして、
これからの寒くなる冬に向けて、
心身ともにリセットします。
昨日は雄で、
美味しい料理をたくさんいただきました。
フグも神戸牛も、
明石のタコに渡り蟹、
満喫しました。
しかしゴルフは、
名門廣野ゴルフ倶楽部に、
完璧に跳ね返されてしまいました。
何度挑戦しても未熟さを教えてくれます。
その一方で今度こそと、
ファイトが湧き上がります。
来年はぜひとも雄&廣野ゴルフ倶楽部、
ご一緒しましょう。
みよさん。
来月の室蘭は練成会の研修ですので、
残念ながら一般公開ではありません。
またの機会によろしくお願いします。
日本ネコさん。
来年は神戸での試合では、
必ず雄で食事をしますので、
お会い出来れば良いですね。
楽しみにしています。
今は新幹線で東京に向かっています。
明日もスケジュールが空いていますので、
たまっている雑用を片付けて、
明後日からの過密スケジュールへの準備です。
ウォークトレーニングもできていないので、
砧公園でしっかり身体を動かして、
これからの寒くなる冬に向けて、
心身ともにリセットします。
質問にお答えします
2011年08月19日
桑ファンさんへ
今日の東スポの記事、私も読みました。
A選手にいじめがあるとの記事に対して、
桑原選手のファンの桑ファンさんからコメントいただきました。
桑原選手のことに対するいじめがあったように書かれていますが、
そのようなことはありません。
桑原選手は指導者も選手達も認めるチームのムードメーカーです。
その桑原選手に厳しく指導する時もありますが、
時には冗談を言いますし、
また冗談には桑原選手も冗談で切り返してきます。
厳しさもあり、
お互い冗談の言い会える良好な関係にあります。
今回のような記事で一番困惑しているのは桑原選手自身だと思います。
人間関係や事実関係を確認せず、
いろんな憶測で判断されることは残念です。
もし桑原選手がいじめられていると言うならば、
それは監督である私の責任です。
しかしそのような事実はありませんし、
また記事にあるように他の選手が、
私の所に直訴してきたようなこともありません。
今回もたくさんのコメントをいただいていますが、
いじめがあるような事実はまったくありません。
くれぐれも心配ないようよろしくお願いします。
今日の東スポの記事、私も読みました。
A選手にいじめがあるとの記事に対して、
桑原選手のファンの桑ファンさんからコメントいただきました。
桑原選手のことに対するいじめがあったように書かれていますが、
そのようなことはありません。
桑原選手は指導者も選手達も認めるチームのムードメーカーです。
その桑原選手に厳しく指導する時もありますが、
時には冗談を言いますし、
また冗談には桑原選手も冗談で切り返してきます。
厳しさもあり、
お互い冗談の言い会える良好な関係にあります。
今回のような記事で一番困惑しているのは桑原選手自身だと思います。
人間関係や事実関係を確認せず、
いろんな憶測で判断されることは残念です。
もし桑原選手がいじめられていると言うならば、
それは監督である私の責任です。
しかしそのような事実はありませんし、
また記事にあるように他の選手が、
私の所に直訴してきたようなこともありません。
今回もたくさんのコメントをいただいていますが、
いじめがあるような事実はまったくありません。
くれぐれも心配ないようよろしくお願いします。
質問にお答えします
2010年12月17日
新米コーチさん
お悩みの様子ですね。
子供達が短期間で結果を出せたのは、
新米コーチさんの指導方針、
方法が実を結んだのだと思います。
おめでとうございます。
子供達が伸び伸びと楽しく練習し、
そして試合することが一番成長する方法です。
このやり方で成果を出したのであれば、
もっと厳しく、怒ったり、指示命令したほうが、
より強くなると考えるのは短絡的です。
ファイターズでも同じようなことが何度もありました。
結果が出始めると、
もっと強くなるには「今のやりかたでは甘い」
と批判されたりしました。
指示命令、恫喝、猛練習は見栄えは厳しそうですが、
これは本当の意味での厳しさではありません。
大人が子供を、指導者が選手に、
怒声罵声を浴びせて厳しくすることは一番簡単です。
しかし子供達にやる気を植え付け、
向上心に満ち溢れた選手になるには、
指示命令、恫喝、猛練習では芽生えません。
子供達が指示命令ではなく、
「もっと上手くなりたい」「強くなりたい」
と思うようになり、
向上心旺盛になることで集中して練習に取り組めるようになるには、
根気良く指導することが大切です。
指示命令、恫喝では短期的には結果が出ても、
長い将来を考えれば問題があります。
古今東西、老若男女、
自らのやる気が一番の原動力です。
指示命令、恫喝、
やらされてやっていることは長続きしないことは、
これまでの歴史が証明しています。
新米コーチさん。
信念を貫いて取り組んでください。
そして何度も話し合いをすることです。
大切なのは指導をする側ではなく、
指導される側の子供達を優先に考えることです。
礼節、思いやり、自己犠牲の精神を大切に指導することは必要です。
当然厳しさも必要でしょう。
しかし、練習や試合の結果を叱責したり、
恫喝することは厳しい指導とはいえません。
結果を出せなくて一番悔しい思いをしているのは選手、子供達です。
結果を出させてあげるのが指導者の仕事ですから、
選手、子供達が結果が出ないときに
一番責任を感じなければいけないのが指導者です。
責めるべきは自分自身であり、
それを一番ショックを受けている選手、子供を責めるのは、
まったく的外れといえるでしょう。
厳しさの本質を良く考えて指導することが大切です。
新米コーチさんのような指導者がたくさん増えることが、
子供達には必要です。
いつも応援していますので、
信念を貫いて、選手、子供達のために行動してください。
お悩みの様子ですね。
子供達が短期間で結果を出せたのは、
新米コーチさんの指導方針、
方法が実を結んだのだと思います。
おめでとうございます。
子供達が伸び伸びと楽しく練習し、
そして試合することが一番成長する方法です。
このやり方で成果を出したのであれば、
もっと厳しく、怒ったり、指示命令したほうが、
より強くなると考えるのは短絡的です。
ファイターズでも同じようなことが何度もありました。
結果が出始めると、
もっと強くなるには「今のやりかたでは甘い」
と批判されたりしました。
指示命令、恫喝、猛練習は見栄えは厳しそうですが、
これは本当の意味での厳しさではありません。
大人が子供を、指導者が選手に、
怒声罵声を浴びせて厳しくすることは一番簡単です。
しかし子供達にやる気を植え付け、
向上心に満ち溢れた選手になるには、
指示命令、恫喝、猛練習では芽生えません。
子供達が指示命令ではなく、
「もっと上手くなりたい」「強くなりたい」
と思うようになり、
向上心旺盛になることで集中して練習に取り組めるようになるには、
根気良く指導することが大切です。
指示命令、恫喝では短期的には結果が出ても、
長い将来を考えれば問題があります。
古今東西、老若男女、
自らのやる気が一番の原動力です。
指示命令、恫喝、
やらされてやっていることは長続きしないことは、
これまでの歴史が証明しています。
新米コーチさん。
信念を貫いて取り組んでください。
そして何度も話し合いをすることです。
大切なのは指導をする側ではなく、
指導される側の子供達を優先に考えることです。
礼節、思いやり、自己犠牲の精神を大切に指導することは必要です。
当然厳しさも必要でしょう。
しかし、練習や試合の結果を叱責したり、
恫喝することは厳しい指導とはいえません。
結果を出せなくて一番悔しい思いをしているのは選手、子供達です。
結果を出させてあげるのが指導者の仕事ですから、
選手、子供達が結果が出ないときに
一番責任を感じなければいけないのが指導者です。
責めるべきは自分自身であり、
それを一番ショックを受けている選手、子供を責めるのは、
まったく的外れといえるでしょう。
厳しさの本質を良く考えて指導することが大切です。
新米コーチさんのような指導者がたくさん増えることが、
子供達には必要です。
いつも応援していますので、
信念を貫いて、選手、子供達のために行動してください。
質問にお答えします
2010年05月25日
おかめさん
子供の指導ご苦労様です。
質問をいただいたのですが年齢やレベル、
現状のフォームが解らないので的確な答えは難しいのですが、
トップの位置とはテークバックから振り出す所がトップです。
このトップの位置はインパクトゾーンから遠ければ遠いほどいいのです。
右打者ですと左腕が伸びた状態(無理やり力を入れて伸ばそうとするのではなく)
くらいがいいと思います。
少年野球を見ていると最短距離に出そうとして、
トップが小さく、腕が縮こまったことが多いのが現実です。
トップは大きすぎることが問題になることはありません。
大きければ大きいほどいいと思います。
また割れとは多くの専門書が勘違いをしています。
割れを作ろうとして上半身がテークバックをしているときに、
足を踏み出しそうとしているケースが多く見られます。
割れと称して体重が後ろ足に残ったまま、
前足だけをステップすることは間違えた理論です。
これではパワーをためることができず、
またタイミングも取れません。
テークバックでは上半身も下半身も捕手方向に引き(頭も一緒に動くのが自然です)、
体重を後ろ足に乗せた状態でトップの形を作り、
その上半身の形を崩さずにそのまま前足に体重移動していけば正しい割れができます。
注意するべきことは体重移動するときに、
上半身の形が崩れたり、ステップしながらバットスイングが始まることです。
これでは強く振り出せないばかりか、
ボールとの距離がとれません。
俗に言う突っ込むとは、
ステップするときにトップの形が崩れてバット(上半身だけが)
がインパクトゾーンに近づくことです。
テークバックでできた形を崩さずにそのままステップすることができれば、
どれだけ体重移動しても問題ありません。
ファイターズであれば稲葉、田中賢介選手のように、
構えたときにすでにトップに近い形を作っておくことをお勧めします。
そしてそのままテークバックで後ろ足に体重を移動させ、
上半身の形を崩さないまま前足に体重移動させることは動きを単純化させます。
また子供達にはトップや割れを意識させることよりも、
強く振ることや遠くに飛ばすことだけを意識させるほうが有効です。
これを意識することで自然に大きなトップ、
しっかりとした体重移動を身につけることができます。
ボールに当てようとする意識がトップを小さくしたり、
上半身が突っ込んだりするので、
まずはしっかりと振ることを意識することが大切です。
ボールを打ちながら直すのではなく、
素振りやティバッティングを繰り返すほうがいいと思います。
子供を指導することは大変ですし、
また将来に関わってくる大きな責任を背負っています。
その一方で子供の成長をサポートすることは大きな喜びであり、
何よりの楽しみ、遣り甲斐です。
これからもがんばって指導していただければと思います。
また何時でも質問してください。
私で答えられる範囲で協力したいと思います。
子供の指導ご苦労様です。
質問をいただいたのですが年齢やレベル、
現状のフォームが解らないので的確な答えは難しいのですが、
トップの位置とはテークバックから振り出す所がトップです。
このトップの位置はインパクトゾーンから遠ければ遠いほどいいのです。
右打者ですと左腕が伸びた状態(無理やり力を入れて伸ばそうとするのではなく)
くらいがいいと思います。
少年野球を見ていると最短距離に出そうとして、
トップが小さく、腕が縮こまったことが多いのが現実です。
トップは大きすぎることが問題になることはありません。
大きければ大きいほどいいと思います。
また割れとは多くの専門書が勘違いをしています。
割れを作ろうとして上半身がテークバックをしているときに、
足を踏み出しそうとしているケースが多く見られます。
割れと称して体重が後ろ足に残ったまま、
前足だけをステップすることは間違えた理論です。
これではパワーをためることができず、
またタイミングも取れません。
テークバックでは上半身も下半身も捕手方向に引き(頭も一緒に動くのが自然です)、
体重を後ろ足に乗せた状態でトップの形を作り、
その上半身の形を崩さずにそのまま前足に体重移動していけば正しい割れができます。
注意するべきことは体重移動するときに、
上半身の形が崩れたり、ステップしながらバットスイングが始まることです。
これでは強く振り出せないばかりか、
ボールとの距離がとれません。
俗に言う突っ込むとは、
ステップするときにトップの形が崩れてバット(上半身だけが)
がインパクトゾーンに近づくことです。
テークバックでできた形を崩さずにそのままステップすることができれば、
どれだけ体重移動しても問題ありません。
ファイターズであれば稲葉、田中賢介選手のように、
構えたときにすでにトップに近い形を作っておくことをお勧めします。
そしてそのままテークバックで後ろ足に体重を移動させ、
上半身の形を崩さないまま前足に体重移動させることは動きを単純化させます。
また子供達にはトップや割れを意識させることよりも、
強く振ることや遠くに飛ばすことだけを意識させるほうが有効です。
これを意識することで自然に大きなトップ、
しっかりとした体重移動を身につけることができます。
ボールに当てようとする意識がトップを小さくしたり、
上半身が突っ込んだりするので、
まずはしっかりと振ることを意識することが大切です。
ボールを打ちながら直すのではなく、
素振りやティバッティングを繰り返すほうがいいと思います。
子供を指導することは大変ですし、
また将来に関わってくる大きな責任を背負っています。
その一方で子供の成長をサポートすることは大きな喜びであり、
何よりの楽しみ、遣り甲斐です。
これからもがんばって指導していただければと思います。
また何時でも質問してください。
私で答えられる範囲で協力したいと思います。
質問にお答えします
2010年03月26日
オクラさんへ
ツイスト打法は身体の開きを抑える事で、
変化球で体勢を崩されたときの対応も可能になります。
また身体の開きを抑えることで、
ヒッティングポイントが近くなるので、
あらゆる球種、状況に対応することにもつながります。
基本的にツイストの動きができるようになれば、
ノーマルなスイングの中にも必ずこの動きが入るようになります。
そのため意識して使い分けなくても、
咄嗟の時に必要であればツイストの動きができます。
ツイスト打法は多くの選手が取り入れていますが、
意識するポイントは選手によって違っても大丈夫です。
ベタ足にすること、前足の膝、後ろ足の踵、腰のツイストなど、
選手が意識しやすい、
また動かしやすいところでツイストを強調すればいいのです。
メジャーリーグでも頭の動きを意識することで、
前足の膝にツイストの動きが入っている選手が多いのです。
またツイストに取り組まなくても、
無意識にこの動きができている選手も沢山います。
これはバッティグのいい選手に共通する動きであり、
その動きを強調することを取り入れた練習方法です。
小学生や中学生くらいでは、
まだこの意識は必要ないのではと思います。
3月28日から、4泊5日の日程で台湾に行って来ます。
台湾外務省の依頼を受け、
日本と台湾の交流を深める一環として、
北海道の中学生チームを引率して行きます。
台湾チームとの合同練習、そして親善試合も組まれています。
昨年の5月にも台湾に行ってきましたので、
今回が2回目の渡台になります。
食事も美味しく、親日的で皆さんとても親切です。
また日本語を上手にしゃべる方が沢山いますので安心です。
今回は久しぶりに集中的に指導しますので、
今から楽しみで仕方ありません。
台湾チームのレベルも高く、
リトルリーグでは世界制覇の経験もあるようです。
日本に来た台湾プロ選手にも素晴らしい選手が多く、
中学生といえども直接指導できることは勉強になります。
今日、明日は千葉マリン、
そして明後日からは台湾です。
ツイスト打法は身体の開きを抑える事で、
変化球で体勢を崩されたときの対応も可能になります。
また身体の開きを抑えることで、
ヒッティングポイントが近くなるので、
あらゆる球種、状況に対応することにもつながります。
基本的にツイストの動きができるようになれば、
ノーマルなスイングの中にも必ずこの動きが入るようになります。
そのため意識して使い分けなくても、
咄嗟の時に必要であればツイストの動きができます。
ツイスト打法は多くの選手が取り入れていますが、
意識するポイントは選手によって違っても大丈夫です。
ベタ足にすること、前足の膝、後ろ足の踵、腰のツイストなど、
選手が意識しやすい、
また動かしやすいところでツイストを強調すればいいのです。
メジャーリーグでも頭の動きを意識することで、
前足の膝にツイストの動きが入っている選手が多いのです。
またツイストに取り組まなくても、
無意識にこの動きができている選手も沢山います。
これはバッティグのいい選手に共通する動きであり、
その動きを強調することを取り入れた練習方法です。
小学生や中学生くらいでは、
まだこの意識は必要ないのではと思います。
3月28日から、4泊5日の日程で台湾に行って来ます。
台湾外務省の依頼を受け、
日本と台湾の交流を深める一環として、
北海道の中学生チームを引率して行きます。
台湾チームとの合同練習、そして親善試合も組まれています。
昨年の5月にも台湾に行ってきましたので、
今回が2回目の渡台になります。
食事も美味しく、親日的で皆さんとても親切です。
また日本語を上手にしゃべる方が沢山いますので安心です。
今回は久しぶりに集中的に指導しますので、
今から楽しみで仕方ありません。
台湾チームのレベルも高く、
リトルリーグでは世界制覇の経験もあるようです。
日本に来た台湾プロ選手にも素晴らしい選手が多く、
中学生といえども直接指導できることは勉強になります。
今日、明日は千葉マリン、
そして明後日からは台湾です。
質問にお答えします
2010年03月18日
ニャムさま
鎌ヶ谷で確かにポップコーンを5個も抱えて、
スタンドを歩いていました。
友達にいろんな味のポップコーンを勧めていました(笑)。
ニャムさんも、そして球場などで私に気がついた方は、
いつでも気軽に声をかけてください。
「ブログ見ています」などと声をかけていただけると、
より嬉しく思います。
これからはどうぞ遠慮なく。
またお会いしましょう。
悠さま
武田勝投手の特徴は、
チェンジアップやコントロールも持ち味ですが、
何よりの武器は投球フォームに隠されています。
武田勝投手のテークバックは、
少年野球などではお手本にはできませんが、
プロ野球選手としては大きな武器になっています。
普通の投手のように流れるようなフォームではなく、
テークバックで一度止まるような動きが入ります。
その時に打者からは手の動きが見えないので、
タイミングが合わせづらいのです。
打者にとって、タイミングを合わせづらいことは大きな問題です。
独特のフォームが武田勝投手の大きな特徴であり、
そして武器になっています。
また、もう一つの特徴は淡々と表情を変えずに投げるところです。
どのような状況でも表情が変わらないことは、
投手としては必要な部分でもあります。
持ち球やコントロールなどだけでなく、
プロ野球で成功するには何か大きな特徴、武器を持つことも必要です。
武田勝投手は今年も安定した成績を残すのではないでしょうか。
チームにとって心強い、計算できる投手です。
鎌ヶ谷で確かにポップコーンを5個も抱えて、
スタンドを歩いていました。
友達にいろんな味のポップコーンを勧めていました(笑)。
ニャムさんも、そして球場などで私に気がついた方は、
いつでも気軽に声をかけてください。
「ブログ見ています」などと声をかけていただけると、
より嬉しく思います。
これからはどうぞ遠慮なく。
またお会いしましょう。
悠さま
武田勝投手の特徴は、
チェンジアップやコントロールも持ち味ですが、
何よりの武器は投球フォームに隠されています。
武田勝投手のテークバックは、
少年野球などではお手本にはできませんが、
プロ野球選手としては大きな武器になっています。
普通の投手のように流れるようなフォームではなく、
テークバックで一度止まるような動きが入ります。
その時に打者からは手の動きが見えないので、
タイミングが合わせづらいのです。
打者にとって、タイミングを合わせづらいことは大きな問題です。
独特のフォームが武田勝投手の大きな特徴であり、
そして武器になっています。
また、もう一つの特徴は淡々と表情を変えずに投げるところです。
どのような状況でも表情が変わらないことは、
投手としては必要な部分でもあります。
持ち球やコントロールなどだけでなく、
プロ野球で成功するには何か大きな特徴、武器を持つことも必要です。
武田勝投手は今年も安定した成績を残すのではないでしょうか。
チームにとって心強い、計算できる投手です。
質問にお答えします
2010年03月13日
おかめさんへ
バッティグの技術のことですが、
おかめさんが仰るとおり体重移動、
そして回転運動をタイミングよく行なうことがバット軌道を作ります。
そしてバット軌道は、インパクトゾーンの前後はボールの軌道に対してレベル、
地面に対してはアッパースイングになります。
ボールの軌道にバットを降ろしてくることをダウンスイング、
そしてダウンからアッパーに移行する時に回転運動が必要になります。
ボールの軌道までバットを降ろしてきた後に、
前足軸に対して回転運動することで、
インサイドアウトのバット軌道も得ることができます。
後ろ足軸にして回転運動することはアウトサイドインのバット軌道になり、
ボールとのコンタクトする接点がワンポイントになります。
インパクトゾーンでのダウンスイング、アウトサイドインのバット軌道は、
ボールとバットがコンタクトする可能性が低くなります。
ボールの軌道にスクウェアなインパクトゾーンでの軌道、
インサイドアウトのバット軌道は、
ボールとのコンタクトするポイントが長く、沢山できます。
打てるようになるにはバットスイングの軌道を、ボールの軌道に合わせること、
そしてバットスピードを上げることです。
この両方を獲得するには体重移動と回転運動は必要不可欠なのです。
体重移動、そして回転運動という順番になります。
体重移動を受け止めることで左サイドに回転軸(右打者)を作り、
左サイドの回転軸に対して右サイドを動かしていくことで
インサイドアウトの軌道ができるのです。
表現方法や、感覚の違いはありますが、
求めるべきものはバットとボールのコンタクトする接点を長く、広く、多くすることです。
技術を文章で表現することは難しいのですが、
今年はいろんな発信をしたいと思っています。
ベースボールマガジン社から
「ヒットエンドラン」という月刊誌が発刊されています。
そこに「野球界の常識、正しいとされてきている基本をもう一度確認する必要がありますね」
と提言し、常識や基本とされてきたことについて、
本当に正しいのかどうかについて毎月連載することになりました。
これまでもこのブログで発信してきたこともありますし、
もっとたくさんの技術についても切り込んでいきます。
興味のある方は参考にしていただければと思います。
バッティグの技術のことですが、
おかめさんが仰るとおり体重移動、
そして回転運動をタイミングよく行なうことがバット軌道を作ります。
そしてバット軌道は、インパクトゾーンの前後はボールの軌道に対してレベル、
地面に対してはアッパースイングになります。
ボールの軌道にバットを降ろしてくることをダウンスイング、
そしてダウンからアッパーに移行する時に回転運動が必要になります。
ボールの軌道までバットを降ろしてきた後に、
前足軸に対して回転運動することで、
インサイドアウトのバット軌道も得ることができます。
後ろ足軸にして回転運動することはアウトサイドインのバット軌道になり、
ボールとのコンタクトする接点がワンポイントになります。
インパクトゾーンでのダウンスイング、アウトサイドインのバット軌道は、
ボールとバットがコンタクトする可能性が低くなります。
ボールの軌道にスクウェアなインパクトゾーンでの軌道、
インサイドアウトのバット軌道は、
ボールとのコンタクトするポイントが長く、沢山できます。
打てるようになるにはバットスイングの軌道を、ボールの軌道に合わせること、
そしてバットスピードを上げることです。
この両方を獲得するには体重移動と回転運動は必要不可欠なのです。
体重移動、そして回転運動という順番になります。
体重移動を受け止めることで左サイドに回転軸(右打者)を作り、
左サイドの回転軸に対して右サイドを動かしていくことで
インサイドアウトの軌道ができるのです。
表現方法や、感覚の違いはありますが、
求めるべきものはバットとボールのコンタクトする接点を長く、広く、多くすることです。
技術を文章で表現することは難しいのですが、
今年はいろんな発信をしたいと思っています。
ベースボールマガジン社から
「ヒットエンドラン」という月刊誌が発刊されています。
そこに「野球界の常識、正しいとされてきている基本をもう一度確認する必要がありますね」
と提言し、常識や基本とされてきたことについて、
本当に正しいのかどうかについて毎月連載することになりました。
これまでもこのブログで発信してきたこともありますし、
もっとたくさんの技術についても切り込んでいきます。
興味のある方は参考にしていただければと思います。
質問にお答えします
2010年02月24日
モトさんへ
バッティングにおけるスイング軌道は、
ダウンスイングからアッパースイングに移行していくので、
レベル軌道になることはほとんどないといってもいいと思います。
インパクトゾーンでのバット軌道は、
投球の軌道に対して一致することが最高です。
つまり投球の軌道は上から下へ緩やかな軌道で落ちてきます。
その軌道にバットの軌道を合わせるには、
地面て対しては下から上への軌道になります。
ボールの軌道までバットを下ろしてくることをダウンスイング、
ボールの軌道までバットが下りてくれば、
後はボールの軌道に沿ってアッパースイングになるのです。
アッパースイングと表現することは誤解を招くかもしれませんが、
あくまでもボール軌道に対してバットの軌道を合わせることが必要ですので、
ボールの軌道に対してレベルスイングと表現すれば納得していただけるのではないでしょうか。
高い位置に構えているバットの芯を、
ボールの軌道まで下ろしてくることがダウンスイング、
そしてインパクトゾーンに向って振り上げることを
レベルスイングと説明すれば問題は小さいのです。
しかし野球界にはダウンスイング信仰が強いので、
アッパースイングを奨励すれば反発されることがあります。
古今東西、成績の残っている打者のバット軌道はボールの軌道に対してレベルスイング、
地面に対してはアッパースイングです。
意識としてはボールの軌道に下ろしてくるところでの
ダウンスイングの意識が強い選手が多いのでしょう。
上から下へ下ろしてくれば、自然とバットは下から上への軌道に戻ってくるのです。
地面に対して水平にレベルスイングを長くすることは難しい動きであり、
バットスピードを出すことも難しいのです。
ダウンスイングを意識すればアッパーに戻り、
アッパースイングをしようとすれば、
一度バットを下に降ろさなければいけないのでダウンスイングが必要になります。
意識の持ち方はどうであれ、
必要なことはボール軌道にバット軌道を合わせることです。
バッティングにおけるスイング軌道は、
ダウンスイングからアッパースイングに移行していくので、
レベル軌道になることはほとんどないといってもいいと思います。
インパクトゾーンでのバット軌道は、
投球の軌道に対して一致することが最高です。
つまり投球の軌道は上から下へ緩やかな軌道で落ちてきます。
その軌道にバットの軌道を合わせるには、
地面て対しては下から上への軌道になります。
ボールの軌道までバットを下ろしてくることをダウンスイング、
ボールの軌道までバットが下りてくれば、
後はボールの軌道に沿ってアッパースイングになるのです。
アッパースイングと表現することは誤解を招くかもしれませんが、
あくまでもボール軌道に対してバットの軌道を合わせることが必要ですので、
ボールの軌道に対してレベルスイングと表現すれば納得していただけるのではないでしょうか。
高い位置に構えているバットの芯を、
ボールの軌道まで下ろしてくることがダウンスイング、
そしてインパクトゾーンに向って振り上げることを
レベルスイングと説明すれば問題は小さいのです。
しかし野球界にはダウンスイング信仰が強いので、
アッパースイングを奨励すれば反発されることがあります。
古今東西、成績の残っている打者のバット軌道はボールの軌道に対してレベルスイング、
地面に対してはアッパースイングです。
意識としてはボールの軌道に下ろしてくるところでの
ダウンスイングの意識が強い選手が多いのでしょう。
上から下へ下ろしてくれば、自然とバットは下から上への軌道に戻ってくるのです。
地面に対して水平にレベルスイングを長くすることは難しい動きであり、
バットスピードを出すことも難しいのです。
ダウンスイングを意識すればアッパーに戻り、
アッパースイングをしようとすれば、
一度バットを下に降ろさなければいけないのでダウンスイングが必要になります。
意識の持ち方はどうであれ、
必要なことはボール軌道にバット軌道を合わせることです。
質問にお答えします
2010年02月19日
ブリの友人さんへ
内野手の捕球時の足の位置ですが、左足前が基本です。
右足を出したほうがスローイングが早いと考えている方がいるようですが、
これは特殊なケースだけです。
それも高度なテクニックが必要であり、
リスクの高いプレーです。
左足を前にして捕球することが大切です。
その時に動きを止めるのではなく、
左足踵からつま先に体重を移動しながら、
すでに右足が前に出るくらいのタイミングで捕れれば、
送球もへの移行がスムーズになり、
早くて正確なスローイングが可能になります。
野球は早く投げることよりも、正確性のほうが重要です。
ベースの何メートル前でアウトにすることを競う競技ではありません。
アウトになればどのタイミングでもいいのです。
アウトになるタイミングで、何より正確に投げることが先決です。
さて昨日は寺町さやさんへの募金のお願いをしましたが、
多くの方が協力していただいたようで嬉しく思います。
ありがとうございました。
28日の講演会でも募金活動に協力できるよう考えています。
内野手の捕球時の足の位置ですが、左足前が基本です。
右足を出したほうがスローイングが早いと考えている方がいるようですが、
これは特殊なケースだけです。
それも高度なテクニックが必要であり、
リスクの高いプレーです。
左足を前にして捕球することが大切です。
その時に動きを止めるのではなく、
左足踵からつま先に体重を移動しながら、
すでに右足が前に出るくらいのタイミングで捕れれば、
送球もへの移行がスムーズになり、
早くて正確なスローイングが可能になります。
野球は早く投げることよりも、正確性のほうが重要です。
ベースの何メートル前でアウトにすることを競う競技ではありません。
アウトになればどのタイミングでもいいのです。
アウトになるタイミングで、何より正確に投げることが先決です。
さて昨日は寺町さやさんへの募金のお願いをしましたが、
多くの方が協力していただいたようで嬉しく思います。
ありがとうございました。
28日の講演会でも募金活動に協力できるよう考えています。